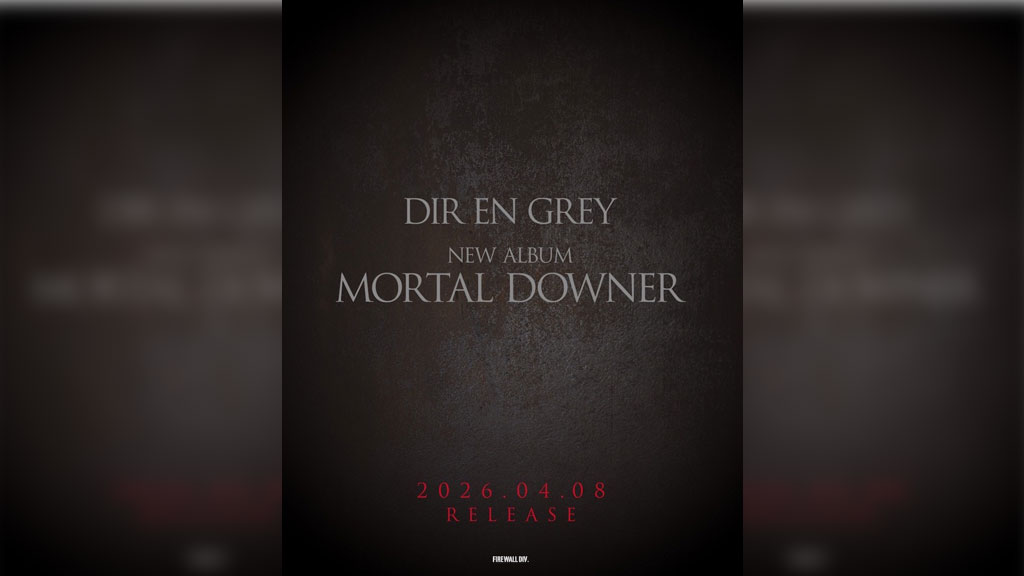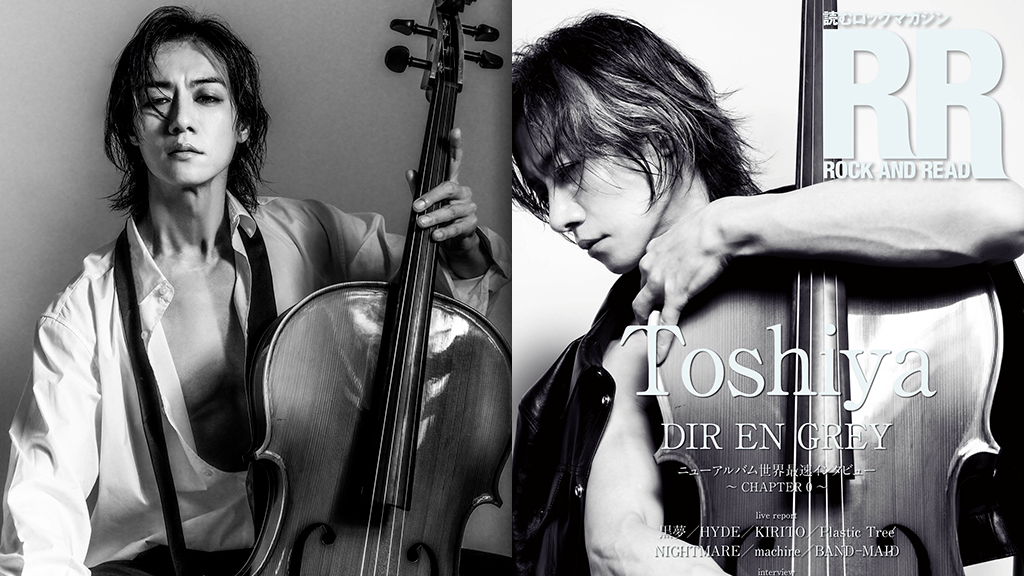DIR EN GREY『UROBOROS』再来に寄せて

1月11日、DIR EN GREYのアルバム『UROBOROS [Remastered & Expanded]』がリリースされた。その表題からも明らかであるように、この作品は2008年11月に発表された『UROBOROS』の“拡張リマスター盤”とでもいうべきもので、その“拡張”ぶりに特筆すべきものがある。リマスターという言葉から単純な音質向上のみを想像/期待して接すれば、オリジナル音源をじっくりと聴き込んできた人たちほど大きな衝撃をおぼえることになるだろう。
事実関係を整理しておくと、DIR EN GREYにとっての現時点での最新作は、通算8作目のオリジナル・アルバムにあたる『DUM SPIRO SPERO』(2011年8月発売)であり、『UROBOROS』はその前作ということになる。そして、その最新作で手腕をふるっていたエンジニア、チュー・マッドセンによる新たなミックスを経たうえでリマスターされたのが、今回の『UROBOROS』新装盤の音源というわけだ。当然ながらバンド側がこうした局面においてマッドセンを起用したのは、『DUM SPIRO SPERO』での彼の仕事ぶりに満足しているからに他ならない。つまり、最新作をもって到達することができた“現時点における、限りなく理想に近い音像”での『UROBOROS』再体現。今作をめぐる彼らの動機/目的はそこにある。
単純に言えば、『UROBOROS』という作品が誕生から3年と少々を経て、現在形のDIR EN GREYに相応しいものとしてアップデートされている、ということでもある。が、今作が伝えてくれる衝撃は、繰り返しになるが、「エンジニアの違いでここまで音質が向上するのか!」といった次元のものではない。昨今、いわゆる歴史上の愛着深い名盤アルバムが高音質CDなどで再発された際などに、「かつて聴こえなかったはずの音が、聴こえてくること」に驚かされることが少なからずあるが、今回の『UROBOROS』新装盤に触れてみると、ミキシングやマスタリングといったプロセスのあり方ひとつで、音像の立体感や奥行きのみならず、温度感や色調まで左右されることがあるという事実を思い知らされる。オリジナル音源との差異がことに顕著なのは、ドラムとヴォーカルの聴こえ方ということになるだろうか。楽曲によっては改めて録音し直されたのではないかと疑いたくなるような箇所すらもある。が、実際、そうした追加レコーディングは一切行われていないし、バンド側にそうした時間的余裕があるはずもなかったことは、彼らの動向を注視し続けてきたファンこそがいちばんよく知っているはずだ。
念のため補足しておくと、今回の新装盤には、オープニングSEにあたる「SA BIR」がロング・ヴァージョンに差し替えられている点、「BUGABOO」の導入に「BUGABOO RESPIRA」が据えられている点、シングルのカップリング音源だった「HYDRA -666-」が途中に挿入されている事実や、「GLASS SKIN」と「DOZING GREEN」が日本語詩によるヴァージョンで収録されていることなど、オリジナル盤とのあからさまな相違点もいくつか見つけることができる。が、そうした目に見える具体的な“拡張”以上に、結果的にこの新音源が孕むことになった説得力の大きさに意義があるように思う。そして何よりも重要なのは、DIR EN GREYが今回のような行為に踏み切った理由が、いわゆる後悔の念などではなく、「過去形の満足を遥かに超越する現在形の充実」にあるということだろう。
もうひとつ明らかなこと。それは、『UROBOROS』の存在なしに『DUM SPIRO SPERO』の誕生はあり得なかったという事実だ。そして、その逆もまた真なり。終わりなきループを意味していたはずの『UROBOROS』の物語は、こうして誰にも予想し得なかった展開を経て、さらにまもなく新たな局面を迎えることになる。1月22日、大阪城ホール。2008年末、初めて怪物の全貌が明かされたのと同じ場所で繰り広げられるライヴ、『UROBOROS -that’s where the truth is-』。それがどんなものになるのか、筆者にはわからない。しかしそれが、過去でも未来でもなく現在だからこそ味わうことができるもの、二度と対峙することができないものであることだけは間違いないだろう。
かつてメンバーの薫は「いつかやりたいなと思っていることは、今やらないと多分できない」という名言を吐いている。その言葉にすべての動機が集約されている気もする。DIR EN GREYは過去を引きずるのでもなく、無闇に未来を約束するのでもなく、今を生き抜こうとしている。その証しともいうべき音に触れ、ステージに向き合うということの大切さを、今、僕は噛みしめたい。もっと直接的に言うならば、とにかくこの新装盤は純新譜と同等に必聴であり、今回のライヴは必見であるということ。圧縮された音楽や、電子の網を通じて伝わってくる情報からは得ることができない何かが、かならずそこにはあるはずだから。
増田勇一