【インタビュー】伊藤銀次、原点回帰でありここから始まる新たな旅への出発点でもあるニューアルバム『RAINBOW CHASER』

聴けばいつでも心躍る“ウキウキミュージック”を極め続けて47年、日本が誇るポップス界のレジェンド伊藤銀次がニューアルバム『RAINBOW CHASER』をリリースした。誰もが知るスタンダード「DOWN TOWN」や、32年間にわたり日本の昼間のテーマ曲だった「ウキウキWATCHING」を始め、ソングライターとしての優れた仕事。さらにソロアーティスト、ギタリスト、アレンジャー、プロデューサーとしての膨大なアーカイブ。全てを超えて軽やかに鳴り響くメロディは、伊藤銀次の原点回帰であり、ここから始まる新たな旅への出発点でもある。アルバムのこと、今のJ-POPのこと、師匠・大瀧詠一のこと、ライブのこと。レコーダーのスイッチを押す前からしゃべりだす、その言葉はどこまでも心地よく滑らかに、音楽のように軽やかに弾んでいる。
■「こぬか雨」が今支持されているのなら原点に還って作ってみよう
■もう一回ゼロから始めるとしたらそれだなと思ったんです
伊藤銀次(以下、伊藤):アメリカでロックが生まれて、その種が世界中に届いたわけですね。今や、世界中にその国のロックがある。そうすると、だんだんとその国の風土に合った音楽になるんですよ。そうなった時に、やっぱり日本人にとっての音楽とは歌を聴くもので、背景にロックっぽい景色がある。それはジャズでもフォークでもディスコでも同じで、背景なんですよ。あくまでリードボーカルを聴くんですね。レッド・ツェッペリンの「胸いっぱいの愛」を説明する時に、“Wanna whole lotta love”って曲知ってる?って言わないでしょ。“ダダーンダダーンダッダッ”って、イントロのリフを言う、あのリフがあの曲なんですよ。洋楽のロックは歌だけじゃなくて、演奏も主役になれる。でも日本ではそれはない。イントロがかっこいいから売れたとか、あんまりないんです。日本に入ってきた時のロックが、風土に合わせて変化して、今のJ-POPが生まれたということですね。
──はい。なるほど。
伊藤:たぶん今のJ-POPというものを外国に持って行ってもわからないと思う。言葉に比重があるから。言葉に比重がある音楽は、言葉が通じないとさっぱりわかんないから。日本人だけですよ、ボブ・ディランが何歌ってるかわからずに人気があるのは(笑)。ただ日本人が凄いのは、サウンドの理解力が凄いところ。洋楽の、言葉はわからなくても、そこにある音楽の良さを理解する力があるんです。
──確かに。
伊藤:だから今回のアルバムの原点となったのは、70年代に僕たちが洋楽を目指して作っていた時の形に、もう一回還ってみたいと思ったことなんです。言葉だけじゃなく、言葉とメロディとサウンドで一つの世界ができているものですね。ここのところ、僕のやっているSNSにメッセージが来るんですよ。アメリカの40代ぐらいの人から、「あなたの『DEADLY DRIVE』を聴いたけど、『こぬか雨』は素晴らしい」とか。ビックリするでしょ? ブラジルの19歳の青年からも、同じメッセージが来たんですよ。YouTubeに誰かが上げていて、それを気に入って、僕の名前を探して来る。前にテレビでやってましたけど、大貫妙子さんの、アメリカ人のファンがいたでしょう。
──はいはい。「YOUは何しに日本へ」でしたね。
伊藤:そうそう。大貫さんのレコードがほしくて日本に来たとか。あとびっくりしたのが、タヒチ80というフランスのポップ・グループが、アコースティックベストみたいなアルバムを出したんですけど、それのボーナストラックに「DOWN TOWN」が入ってるんですよ。しかも日本語で。早速買いに行きました(笑)。
──すごい(笑)。チェックします。
伊藤:だから外国の人でも、ポップスやAOR的な音楽を好きな人は、あの当時の日本の音楽に注目してるみたい。それはどういうことなんだろうな?と思うんだけど、よく考えてみたら、J-POPという音楽が一つの形になったんですね。日本のマーケットの中で、一番効率良く、みんなの支持を得る音楽として確立できたんだけど、それは僕が求めていた音楽ではない。振り返って考えてみると、僕が90年代にウルフルズのプロデュースでやろうとしていたことは、今のJ-POPとは真反対のことだった気がするんですよ。トータス松本くんの歌だけじゃなくて、メンバーが弾いている全ての楽器が、ボーカルと同じぐらいにアピールしている。基本的には洋楽的な作りなんですよ。「そうか、僕の作り方はJ-POPとは全然違うんだ」と思って、そして「こぬか雨」とかが今こういうふうに支持されているのなら、原点に還って作ってみようと。2年前に45周年を迎えて、もう一回ゼロから始めるとしたらそれだなと思ったんです。
──確かに、あの45周年プロジェクト以降、リリースもライブも活発化した印象がありますね。あそこで新しいモチベーションが生まれたのかなと思って見ていました。
伊藤:まあ、あんまり先がないんでね(笑)。
──そんなこと言わないでください(笑)。
伊藤:あと何十年とかあるなら、「今からこうやって、ああやって」って計画も立てられるけど、マラソンで言ったら、一回走って、もう一回走るけどどうする?みたいな話ですから。そしたらやっぱり、今までの経験の中から、自分に一番合っているものをやるべきだなと思うんですね。僕の場合、ボーカル音楽なので、いくらアレンジをかっこよくしても、僕がボーカリストとしてちゃんと成立する音楽を考えなきゃいけないんですよ。ただ僕はアレンジャーでもあるので、それこそ沢田研二さんの「ストリッパー」、アン・ルイスさんの「ラ・セゾン」みたいに、ちょっととんがった過激なアレンジをする人なんですね。僕の中にいるプロデューサーって、すごくうるさい奴なんですよ。一番上昇志向の激しい奴で、だから僕にもそれを歌わせるわけですよ。だけどボーカリストの僕は歌いきれない。ずーっとそんな悩みがあったんだけど、10年ぐらい前かな。生まれて初めて弾き語りで全国を回って、ギター一本と自分の歌を、毎晩自分で聴くわけですね。そこで僕のボーカルというものを、正面から見つめる形になった時に、「これが俺の歌なんじゃないか」というものが、なんとなく見つかってきた。そしてその後、もう七回忌になるのかな、大瀧詠一さんが亡くなられて、それが一つのきっかけになった。

──あれは、2013年の暮でしたね。
伊藤:僕がこの世界に入るきっかけになったのは、大阪で「ごまのはえ」というバンドをやってた時に、ちょうどベルウッド・レコードですね。当時はレコーディングについての知識がなかったもんだから、シングルを作る時にものすごく苦戦したんですね。そして当時、僕が思うに、はっぴいえんどが日本で一番良い音のレコードを作っていた。アレンジも素晴らしくて、まるで洋楽のようだった。それでアルバムを作る時に、細野さんか大瀧さんのどちらかにプロデュースをお願いできたらいいなと思って、メンバーで話し合って、僕たちのカラーには大瀧さんのほうが合っているんじゃないかと。お願いしてみたら、わざわざ大阪までライブを見に来てくださって、「やるよ」と言ってくれた。ただし「東京に出て来るならやる」と。それでメンバー内で喧々諤々あって、じゃあ東京へ行こうと言って、出てきたのが、僕のきっかけなんですね。
──その伝説は、聞いたことがあります。
伊藤:それ以来ずっと、僕は大瀧さんのファンでもあった。亡くなった時に、僕は大瀧さんの何に惹かれたんだろう?と思って、はっぴいえんどのアルバムの1曲目から、ソロの最新作に至るまで、全部たどってみたんですよ。そうするとわかったのは、もちろん曲も、プロデュースも素晴らしい。だけど僕が一番惹かれたのは、歌だったんです。ロックをやる人の中で、あんなにいろんな歌を歌える人はいなかった。特に『ロング・バケーション』以降の歌い方、クルーナーという、昔のビング・クロスビーみたいな、唇をうまく使って柔らかく歌うあの歌い方は、はっぴいえんどの頃からすでにあったんですけど、「僕はこれが好きだったんだ」と、亡くなった時に気が付いたんです。だから僕は、大瀧さんみたいに歌えるかわかんないけど、好きだったこの歌い方を自分の歌に取り入れて、こういう歌い方でやっていこうと思ったのがその時だった。
──はい。なるほど。
伊藤:そして、この前のアルバム『MAGIC TIME』(2017年)を作ったんです。近年は、ソウルがまたすごく好きになってるんです。僕の音楽はソフトだとよく言われるんですけど、よく聴いていただけるとわかると思うけど、リズムが強いんです。でもオーティス・レディングみたいには歌えない。だけどソウルの世界には、柔らかい声で歌う人もいっぱいいる。これからはそういうスタイルでやってみようと思って、作ったのが今回のアルバムです。もっと早くやっておけば良かったと思うけど(笑)。
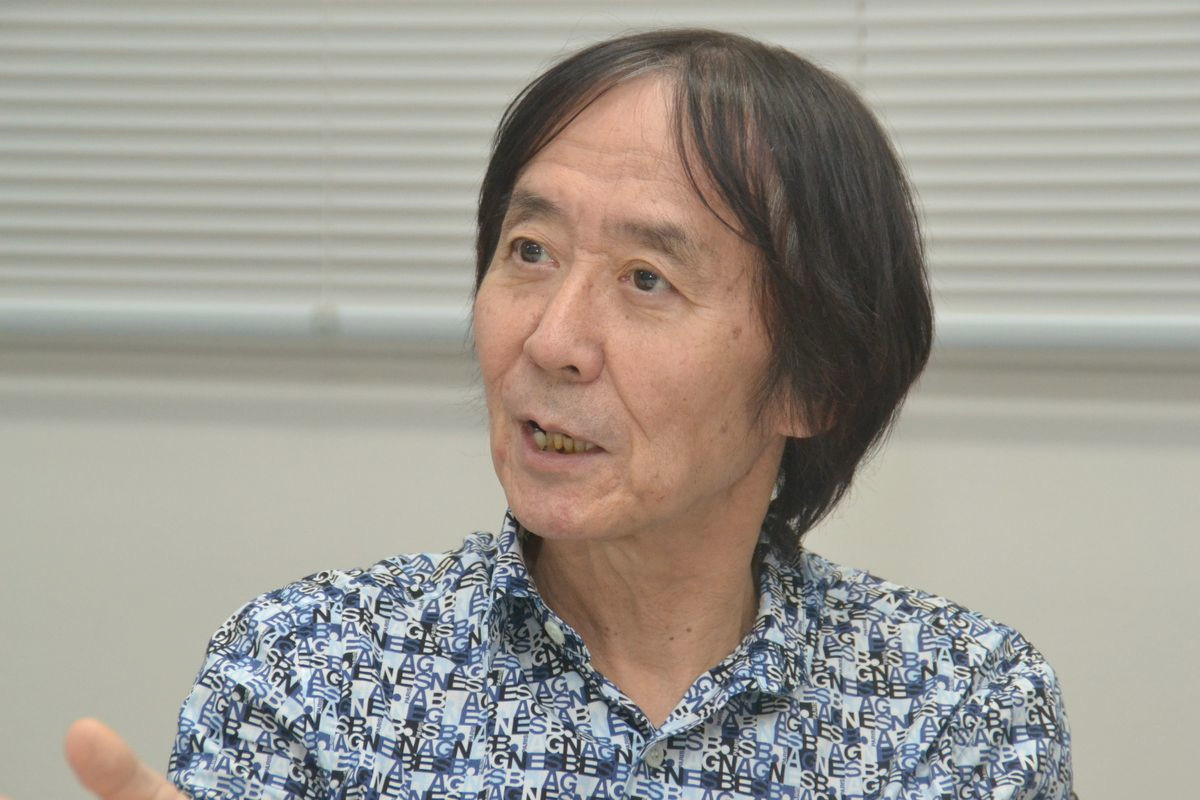
──新曲5曲は、全て書き下ろしですか。
伊藤:そうです。断片的なものを含めると、40曲ぐらい作って5曲選びました。けっこう良い曲がまだあるんで、次にいつ出せるかわかんないけど、そういう曲も詞をつけて、これからライブでやっていこうかなと思っています。
──いわゆる、曲先ですよね。
伊藤:そうですね。ただ僕の場合、♪ラララでは作らないんですよ。でたらめな英語が付いてるんですけど、時には日本語で出て来ることもあって。4曲目に入っている「愛をつかまえて」は、♪恋を抱きしめて、と歌っていたんでよ。昔はそれを全部書き直していたんだけど、これには何か意味があるんじゃないか?と。というのはね、「ココナツ・バンク」(ごまのはえから改名)をやっていた時に、♪ラララ、で聴かせてもメンバーやスタッフに伝わりにくいだろうと思って、♪泣きやんだ空、スクリーン越しに、乾く通り雨、夏が始まる、って、浮かんだ言葉を適当に並べて歌って、聴かせたら、「歌詞、これでいいんじゃない?」って(笑)。(ココナツ・バンク「天気予報図」)
──あはは。まさかの。
伊藤:スクリーンって何なんだ?って、よくわかんないでしょ。ところが人間って面白いもので、「泣きやんだ空」と聞くと、「雨かな」って思うんです。スクリーンは雨のスクリーンかなって、勝手に思っちゃうんですね。でたらめの中にもきっと何かがあるのかなと思って、それからは、適当な言葉で仮歌を歌った後、直さないで、「これってどういう意味だろう」って考えるんですよ。だから♪恋を抱きしめて、も、それっぽい歌が歌いたいんだろうなと。
──深層心理にあるんじゃないかと。
伊藤:今回は、大上段に愛の歌を歌いたかったんです。それはね、ちょっと世の中が、親が子供を殺しちゃったりとか、あるじゃないですか。いろんな事情はあるんだろうけど、なんか殺伐としてきてると思うんです。僕だって生活していれば、そんなに楽しいことばかりではないわけで、誰でもそうだと思うんです。だけど「生きる」ということは、そんなことは日常生活に当たり前のように起こることなんだと。仏教っぽくなりますけど、楽しいことばかり起きてほしいなと思って生きているとすごく辛いんです。楽しいことばかりじゃないから。でも「待てよ。ここを一生懸命が頑張れば、誰かが助けてくれるかもしれない」と。みんな同じですからね。そうやって、楽しいことも辛いこともみんなで分け合って生きて行けばいい。昔の日本はそうだったんじゃないか?と思うんですよ。それを、大げさじゃなく歌いたかったんですね。
──わかります。
伊藤:僕の歌を聴いてくれてる人たちが、そういう歌を聴いて、殺伐とした気分からふっと離れて良い気持になって、また明日生きていこうと思えるように。僕は来年70歳になるんですけど、70歳までポップスをやるなんて本当にありがたいし、みなさんが応援してくださってるおかげですけど、これからどうなるかわからない。でもね、「なんで自分は生きてるんだ?」とか、よく言うじゃないですか。僕は、生まれたことに意味なんかないと思っています。全ての人間は意味なく生まれてきて、でも生きてる間にどう生きるか。自分の心に従って、「俺は楽しく生きたな」というふうに、自分で努力しなきゃいけない。僕はエンタテイナーでもあるので、これからの残りの人生は、もっと積極的に、僕の歌を聴いた人に幸せになってほしい。その喜ぶ顔を見て、僕も幸せになりたい。そうやっていこうと、今回強く思いました。
──その気分は、ものすごく出ていると思います。
伊藤:今までだったら恥ずかしいなという言葉も、あえて歌おうと。ファンタジーですよ。長く生きて思うのは、人間は何らかのファンタジーがないと生きていけないんです。現実を見た時に、良いことも悪いこともあるんだったら、ちょっとでも良いことを、「これいいよね!」って言いたいじゃないですか。平凡だけど、「愛こそはすべて」だと、今回のアルバムでは歌ってみたかったんですよ。今までこんなこと、あんまり思ったことなかったけど。
──オール・ユー・ニード・イズ・ラブ。それこそ銀次さんの原点の、ビートルズが歌ったように。
伊藤:たとえみんなに笑われてもいいから、「愛こそはすべて」だと歌いたかった。お互いに尊敬しあって、助け合って、幸せになることは、とても大切なことだと思うんです。そういう感覚になったのは、最近ソウル・ミュージックをよく聴くようになったからかもしれない。マーヴィン・ゲイ、アル・グリーンとか、みんな愛の素晴らしさを歌ってるので、今回は正面切って歌ってみました。






