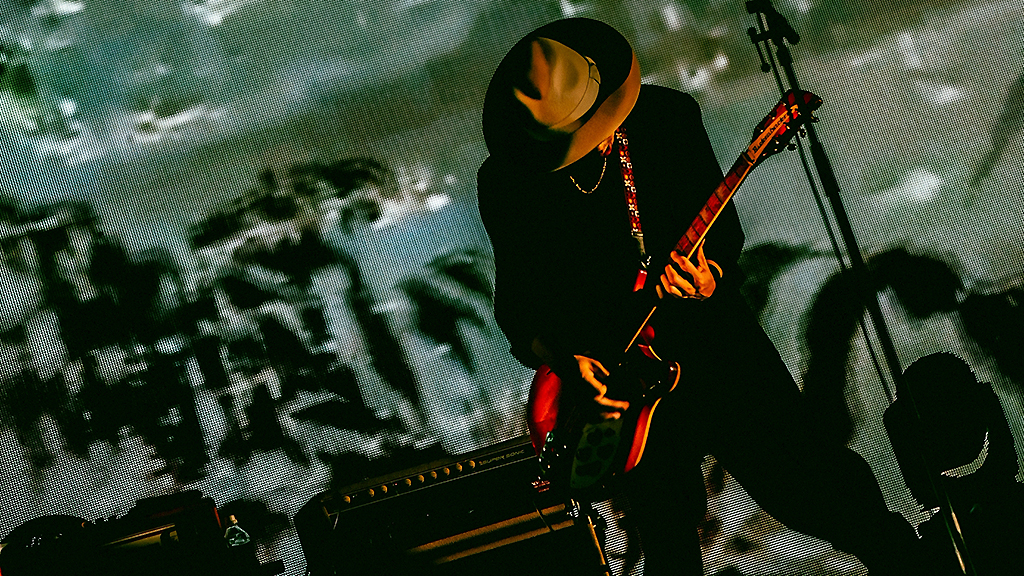【インタビュー】ACIDMAN、大木伸夫が語る『Loop』再現「すでに爆発していた。20年前にこういう作品を残せていた自分が誇らしい」

■必死についてきてくれたふたりのおかげ
■僕の背中を押してくれたんだなって
──25年って、そういう時間の流れを実感する年月ですね。そして今回、2ndアルバム『Loop』発表から20周年を迎えて、最新リマスタリングを施してアナログ盤リリースされます。ファンのなかでもこのアルバムは特別な作品として存在してるんじゃないかなって思うんです。さらに再現ツアーも実施されるということでは、これもまた結成25周年、メジャーデビュー20周年をみんなで祝ういい時間になりそうですね。
大木:そうですね。僕自身、アルバム『Loop』をちゃんと聴いたのが、それこそ20年ぶりくらいなんです。
──そういうものなんですか?
大木:そうですね。今回、アナログ盤リリースにするにあたって、レコード用のマスタリングで、頭から最後まで集中して1枚を聴いたんですけど、すっごくいいアルバムだなと思ったし、改めてすごいバンドだなと思ったし、これも自分がやっていると思えないというかね。自分の言葉とか自分のメロディに思えなくて。よくこんなに叫び倒していたなとか(笑)。歌詞の内容はめちゃくちゃシュールですけど、でも、なんか熱いものを感じるんですよね。今聴いても何ひとつ古くないことに驚きました。青さも感じなかったし、こういうバンドが今出てきたら売れるだろうなという、客観的な感じで聴くこともできましたね。テストバージョンを家のレコードプレイヤーで聴いたらめちゃくちゃよかったんですよね。ストリーミング音源やCD音源ではカットされてしまう高域と低域が出ているから、レコードにしたぶん、すごく肉厚になりましたね。
──当時からバンドの軸というか、音楽や歌詞の世界観が一貫していることも、古くならないというところにつながると思います。
大木:今もそうなんですけど、その時その時の流行りをテーマにしてやることのほうが、むしろ一番苦手で。それをやって何の意味があるんだろう?と思うんです。ひとときの快楽とお金儲けというものにまったく興味がなくて。ずっと聴いてもらえる、ずっとライブに来てもらえる、みたいなものを意識していたんです。それは結成当時から言い続けていましたね、僕は。

──ただ、近年のライブを観ていてすごく親切だなって思うのが、MCとかでも歌詞の世界観について、“こういう視点で物事を見ていて、こういうことを歌っているですよ”ということを言葉にするようになりましたよね。作品を重ねるごとに、歌詞についてもよりシンプルな表現になっていて。
大木:『Loop』の頃って、単語単語で表現していたので、想像させるものであったし、ある意味では突き放しているものでもあって。今もそうですけど僕は、スピリチュアルな世界が大好きで、目に見えない世界やこの世界の本質を暴こうとしているんです。“この人、本当に宇宙から来たんじゃないか?”っていう感覚があるような音楽だと思うので。僕自身、そういう表現で描いてくこともすごく楽しい作業なんだけど、やっぱり子どもたちにもわかってほしいんです、この宇宙の壮大さを。ただ、「宇宙には138億年の歴史があって」と言っても、子どもには億の単位がイメージできないでしょうから、「すげえ広いんだよ」って言ってあげるというか、なるべく言葉をわかりやすく伝えたいというのがあって。それは当時からの目標でもありましたね。ただ、それが下手だったというか、ぶっきらぼうで(笑)。当時から小説『星の王子さま』みたいなものが目標だったし、今もそうなんですよね。簡単だけどよく考えるとすごい世界で、ゾッとするくらい深い。そういうものが描けたらいいなというのは、これからも変わらないテーマですね。
──『Loop』当時は、若さゆえの反抗心みたいなものもあって、シュールな世界が浮き彫りになっていたところもあるんでしょうか?
大木:そうですね。すべてに中指を立てていたと思うし(笑)。
──本当に稀有なバンドだと思うんですよね。デビュー当時はACIDMANのようなバンドはもちろんいなかったし、どう理解されてるのかなっていう不安もあったのかなとも思うんですよ。
大木:不安でしたし、それこそ、この間のアナログ盤のマスタリングまで不安でしたよ(笑)。でも45歳になって、改めて聴いてもめちゃくちゃカッコよかったから、もっとオラオラでいけばよかったなって後悔しました(笑)。やっぱり右往左往してましたからね、当時は自分の考え方も。もっとほかに伝え方があるんじゃないかとか、もっと高い芸術性をとか、爆発しきれていないんじゃないかとか、常に思っていたんですけど、今聴いて、これはもうすでに爆発していた。こういう作品を残せていたことが、自分が誇らしい想いですね。大切な一枚です。
──当時は、そういう不安や壁をどう越えようとしていましたか?
大木:毎日スタジオに入って、メンバーをずっと焚きつけるというか。スタジオに入るんだけど、音を出してる時間は1時間とかしかないんですよ。4〜5時間ずっと説教するというか、「もっとこいよ!」「もっとないのか、お前たちには熱いものが」っていう日々がずっと続いていたんですね。だから、俺が乗り越えたというよりは、必死にそこについてきてくれたふたりのおかげでやりきれたんだと思います。
──まずふたりに理解してもらって?
大木:理解…は正直してくれなかったですね。でも、僕が求めすぎていたんです。たとえば、全然違うジャンルの人に「これをわかってくれよ」とか、言葉はすごく抽象的なのに「理解しろ」と言っても、それは難しかったと思うし。それでも彼らは、理解しようということではなくて、ついてきてくれた。すごくシンプルなことなんです。それだけで僕の背中を押してくれたんだなっていうのは、今は思いますね。
──スタジオの話がありましたが、当時は完成形まできっちりとバンドで練り上げてから、レコーディングに入るという感じでしたか?
大木:それは今も変わらないですね。当時は俺が原型を作っていて、その段階で実は、僕の頭のなかで全部できているんだけど、ふたりからアイデアをいただかないと曲にならないと思っていたんです。でも結局、何も出ないまま1ヶ月後、原型どおりにレコーディングするということが多かったかもしれない。だから、“この1ヶ月間、なんだったんだ”みたいなフラストレーションが半端なくて。“どうしてなにも持ってこないんだ”っていうその期間が無駄だなと思いつつ。でも、今思えばまったく無駄ではなかったというかね。やっと最近ふたりは、俺の世界観をわかってきている感じなので(笑)。20年の時を経て、やっとちょっと理解してくれているので、無駄じゃなかったなと思います。
──3ピースでこのサウンドを構築しているってこと自体がすごいですからね(笑)。『Loop』のアナログ盤は、オリジナルのアナログマスターテープからのリマスターということなんですが、20年前当時というと、デジタルでのレコーディングもあったのでは?
大木:当時はデジタルに移行しつつあった頃ですね。だけど僕たちは、エンジニアの日下貴世志さんがずっとアナログにこだわっていてくれたおかげで、アナログテープ録音をしていたんです。だから、普通の音よりは、非常に生々しいというか、手触りに強い音になっていますね。
──レコーディング手法自体に、デジタルとはまた違った勝負感があるんでしょうか。
大木:それはあるかもな。たとえば「飛光」は、一度録って歌入れからミックスまでしてもらったんですけど、その段階で俺に気に入らないところがあって。「申し訳ない。もう2日ください」とお願いして録り直しをさせてもらっているんです。すごく贅沢な環境でしたよね。無理を言って、イチから音も録り直しましたし。僕自身、新しい技術は使うタイプなので否定はしないんですけど、“この時にしかこの音は録れないだろうな”っていうのはあります。