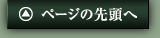レミオロメン、新しいレミオロメンが凝縮したセルフプロデュース・アルバム『花鳥風月』特集
レミオロメン 5thアルバム『花鳥風月』2010月3.3リリース
2本立てインタビュー特集 アルバム『花鳥風月』インタビュー + 映像作品「花鳥風月 Live Movie」インタビュー
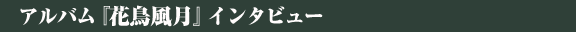
藤巻亮太: そうですね。良くも悪くも、『風のクロマ』というアルバムは、試行錯誤でテーマが膨らんだり色んなものを追い求めていく作業だったし、葛藤も含めて制作作業に入った作品だったから時間もかかった。その後ベストアルバムが出て、ある種、色んなものの整理がついて迎えたのがこの『花鳥風月』なのかなぁと。『風のクロマ』でやり切って、ベストアルバムを出して、結局本当に自分たちがたどってきたことって良いことも悪いことも自分たちのものじゃないですか。そんなベースがあって、今、ここで何ができるかっていうと、その瞬間にあることを全力でやる以外なくて。そこに対してリアリティを持って進めていったのがこの『花鳥風月』の最初のマインドです。そうしたら、すごい身近なものを歌うことが出来たんです。
藤巻: 「花になる」って曲の中にも“運命を受け入れる気になった”って表現がありますよね。起きたことは起きたし、起ることは起るから、だから目の前のことを頑張ろうみたいな曲なんですよね。ちょっと暴力的なロックなんですけど、この曲ができたときに、今生きている日常の中に歌えることがいっぱいあるんじゃないかなと思って、『花鳥風月』という曲もできたんですよ。ただ買い物に行って、野菜を買ってきたら野菜の色がそれぞれで、生きていると言うのもこういうことだよな、と。みんな違うし、なんだか色々だよね……って、もうそれだけなんだけど(笑)。でも、そこにこそ小さな幸せがあったりして。テーマが膨らんでいた時期にはそういうことには気付けなかったし、わからなかったけど、そこから連鎖的にテーマが次々に出て来て。そういう意味で書くのは早かったかもしれないです。以前は一番最後に歌詞を書くことが多かったし、アレンジが全部決まって、歌入れ前に歌詞を書いて、歌詞で最後につなぎ止めるとか、歌詞で全部を包むみたいな感じがあったんです。それはそれでありなんですけど、そうじゃない作り方をしたいと思って、今回はまず、メロディと歌詞を作っておこうと。そこから向かう方向にみんなでアレンジをしていこうって感じだったので、そういう意味での作業上での明確さもありました。

藤巻: うん。やっていきながら理解が深まっていくこともありましたし。よく(前田)啓介が言ってたよね?「大晦日の歌」では蕎麦が出て来るじゃない? その匂いの話…。
前田啓介: そうそう、匂いがある。それを煮詰めて行く感じとか。言葉があると、アレンジがどこに向かって行くかとか、ものすごい明確なんです。これは僕らの1stアルバム『朝顔』のときにやっていたスタンスでもあるんですけど。その中で変わるところもあるんだけど、大枠、向かうところが見えている音楽は、そういう匂いのある音楽になっていきますよね。
神宮司治: 言葉があった方がイメージしやすいです。全員が同じものを見るかはわからないですけど、言葉の中で、自分の中に引っかかるキーワードみたいなものに対して膨らませて、それを音にして表わしていくっていうものは、歌詞があるとないとでは全然違います。最後の曲「小さな幸せ」とか、たいして大きなことを言っているわけじゃないですよね。些細なことを言っているというところで、プレイ的にも派手なことが必要ではない。シンプルに伝えたいことだけを伝えるという意識が演奏にも現われましたよね。
神宮司: うん。歌詞の世界を邪魔しないプレイというのも気をつけました。ロックでガンガン飛ばして行くっていうのとはまた違うんですけど、歌詞の世界観がすごく伝わりやすいものに対しては派手なプレイは避ける。自分の中での勝手なイメージですけど、買い物に行っている雰囲気みたいな(笑)。道を歩く感じとか。駆け足じゃなく、ゆっくり歩いている感じとか。そういう風に自分の中でイメージを作るんですよね。それが音に出たらいいなって思いながらレコーディングしていきました。

藤巻: そうなんですよ。これはうまく行ったよね。
前田&神宮司: うん。
藤巻: 最初、ProToolsで作ったから、機械だと跳ね感が全然出なくて。
前田: そうそうそう。いわゆるジョン・レノンみたいな “ドッタンドッドッタン”みたいなのをみんなでやって。そういうループを作って貼付けたら、グルーヴが一つ決まっていって。そのテーマのもと、パーティー鳴りというか、そういうものになっていきましたね。おもちゃ箱の中を旅するとか、そういう感覚で。3人のノリって、ProToolsの数値では計り知れない何かがあるんですよ。そういうところを感じ合って、一つのグルーヴになる。それは生でやってみないとわからないんです。
藤巻: テイク選びにしてもそうだよね。「花になる」とか「ロックンロール」なんて曲は、みんなの演奏のテンポ感が揃うときだと思うんですよね。クリックに揃うことじゃなく、みんなの解釈しているグルーヴが近いところにあるっていうか。そういうテイクを選んでいく良さっていうのはすごく勉強になったんですよ。
神宮司: 特に速い曲っていうのは、自分で演奏すればするほど慣れて来るじゃないですか。同じことをやれば演奏自体は上手くはなるけど、やらなくていい、と。僕的には次に演奏したらもっと上手くできるかもしれない。だけど、全体的に見たら、今の演奏の方がみんなのグルーヴ感が良い。それを採用する、と。個人的に見たら、やりたいって思うけど、客観的に全部を見たら、そっちの方が良かったんですよね。そういうことは勉強になりましたね。
藤巻: うん。前々もあったと思うんですけどね。これは今回のアルバムでセルフプロデュースしているということにも話がつながって行くと思うんですよ。自分たちの音を自分たちの責任で鳴らす、みたいな。そういう気持ちで臨んでいたレコーディングだったから。より、そういうところで明確に見えたっていうのもありましたね。今まではずっと小林(武史)さんとやってこれて、素晴らしい制作現場で多くのことを学んだし、多くのことを僕らの音楽に注入してくれたと思うんです。その上で、今、自分たちの音楽にきちんと向き合わなければいけない時期だった。ベストアルバムも出して、ここはもう自分たちを追い込んででもセルフプロデュースをやらないといけないと思いましたね。そういうモチベーションで挑めたから、その意識は色んな場面で現われたと思います。生きてることと音楽をやるってことはイコールだと思うんですよ。リアリティを感じていたいっていうかね。音楽を作っていく以上はそれを作るわけがあるというか、生きているという何かを切り取ったものを出していかないと。それは自分の目線でしかないんですけど、そこに責任を持って切り取って、リアリティを獲得していこうってことだから。なかなかそれが手に入らないこともあるけど、コツコツやろうが、勢いでやろうが、それは絶対に必要なものだと思えました。
取材・文●大橋美貴子