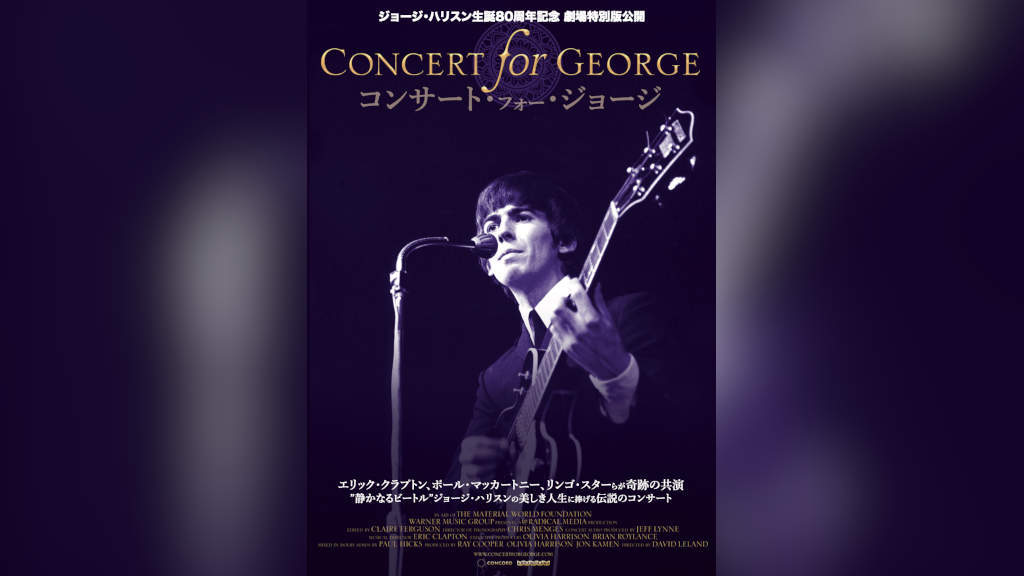【D.W.ニコルズ・健太の『だからオリ盤が好き!』】第35回「『George Harrison / Living In The Material World』徹底考察」

D.W.ニコルズの鈴木健太です。
もう黄金週間も終わり、すっかり初夏ですね。
僕のバンドD.W.ニコルズは、よく春が似合うバンドなんて言われるのですが、きっとこれを読んでいる皆さんも、春とか初夏になると聴きたくなる曲というのがあるのではないのでしょうか。
僕が春から今くらいの季節にかけて最も聴きたくなる曲の一つに、George Harrisonの1973年の曲「Give Me Love」という曲があるのですが、この春、その「Give Me Love」シングルのUK 7inchをついに手に入れました。そしてこの曲が収録されているアルバム『Living In The Material World』のUKオリジナル盤も手に入れました。
今回の「だからオリ盤が好き!」はこの『Living In The Material World』LPのUS・UK盤と「Give Me Love」UK7inchを取り上げます。

ジョージ・ハリスン。
僕の最も好きな音楽家の一人であり、最も好きなギタリストの一人でもあります。
彼の代表作『All Things Must Pass』(1970年発表)については、この連載の第20回「『All Things Must Pass』とウォール・オブ・サウンド」で取り上げました。今回取り上げるアルバム『Living In The Material World』は、その次作となる1973年発表のスタジオ・アルバム。ジョージの作品の中で、僕が最も好きなアルバムです。
前作『All Things Must Pass』では豪華な顔触れのゲストミュージシャンを招いてフィル・スペクターのプロデュースのもとに制作されましたが、この『Living In The Material World』ではその前作とは打って変わって、少数精鋭の“仲間”とも言えるミュージシャンとともに、ジョージのセルフ・プロデュースによって制作されました。
ビートルズ中期以降、その作曲家としての才能をどんどん開花させていったジョージですが、ビートルズ解散後の第一作『All Things Must Pass』で溜まっていたものを一気に放出したことで力が抜けたのか、それから3年後に発表されたこの作品は、“ロックの金字塔”と評された前作とは変わって、自然体で穏やかな雰囲気と優しく美しいメロディーに溢れたものとなっています。
シングル曲「Give Me Love」を始め、神を歌った曲が多いことについての批判的な意見もありますが、その精神性はビートルズ中期以降、生涯を通じてジョージの根幹にあるものであり、彼の音楽とも密接に結びついているものなのです。したがって、神にまつわる曲が多いのは必然であり、だからこそこの美しい楽曲達が生まれたのでしょう。また、ビートルズ時代の軋轢を歌った「Sue Me, Sue You Blues」のように、ユーモアとアイロニーを込めた曲も健在で(ビートルズ時代の「TAXMAN」を思い起こさせます)、自分が俗人であることを見失っていた訳でもありせん。
『Living In The Material World』の音像は当然フィル・スペクターの前作とは違うのですが、オーバーダビングは少なくシンプルです。そうなると当然、一つ一つの楽器がサウンドに占めるウェイトも重くなる訳ですが、このアルバムでは各プレイヤーの演奏が本当に素晴らしく、それも聴き所のひとつです。この年代はSSW(Singer Song Writer)の時代であり、そのバックミュージシャンの演奏が素晴らしいアルバムも数えきれないほどありますが、このアルバムの演奏の素晴らしさはその中でも群を抜いていると思います。
ジム・ケルトナーのドラミングはその中でも特筆すべきもので、数えきれないほどのレコーディング・キャリアのある彼の演奏の中においても、ある意味突出した演奏かもしれません。ジム・ケルトナーと言えば、ヴォーカルに寄り添ってしっかりと支えるドラミングというイメージが強いのですが、このアルバムでの彼のプレイはその枠に収まらないものも多いのです。特に凄いのが「Give Me Love」での演奏。決して派手ではない音使いながらも絶妙なリズム構成でこのフォーキーな楽曲に躍動感とスピード感を与えつつ、グイグイとグルーヴを引っ張っています。
また、ジム・ケルトナーとリンゴ・スターのツインドラムがアルバム中で度々登場するのですが、これがまたカッコイイ。アルバムのダイナミズムに華を添えています。
クラウス・フォアマンのベースはまるで歌うようです。ベースとはリズム楽器でありながらメロディー楽器であることをあらためて教えてくれます。多彩なリズムアプローチに加え、ときに歌いだす独特なベースは、このアルバムのメロディアスな印象に大きく貢献しており、これも密かな聴きどころと言えるでしょう。僕の最も好きなベーシストのひとりでもある彼の素晴らしいベースは、ジョン・レノンやリンゴ・スターのソロ、ジョージの他のソロ作品等でも聴くことができますが、中でもこのアルバムとジョンの『Imagine』での演奏には特に素晴らしいものがあります。ジョージ、ジョン、リンゴの作品に参加していることなどから、70年代にはポールの代わりにクラウス・フォアマンを迎えてビートルズが再結成されるのではと噂されたのは有名な話ですが、彼のベース・プレイから考えてもその噂は納得できるような気がします。
また、彼は画家・イラストレーター・グラフィックデザイナーでもあり、ビートルズのあの『Revolver』のジャケットを手がけたのも実はこのクラウス・フォアマン。“根っからのベーシスト”ではないからこその、歌うようなベースなのかもしれません。
「The Light That Has Light The World」やタイトルトラック「Living In The Material World 」などでは、静と動の両面においてニッキー・ホプキンス節全開のピアノを聴くことができます。このアルバムがリリースされた1973年は、60年代からセッションミュージシャンとして売れっ子だった彼がソロアルバムをリリースした年でもあり、演奏に彼らしさが濃い濃度で出ているのは納得です。
そして、参加ミュージシャンのリストにギタリストはいません。つまりこの作品で聴くことの出来るギターは全てジョージ自身によるものなのです。
前作『All Things Must Pass』収録の代表曲「My Sweet Load」で彼のトレードマークとなったスライド・ギターを始め、美しいアルベジオから小気味良いカッティング、そしてもうひとつのトレードマークでもあるレスリーサウンドのギターまで、ギタリストとしてのジョージ・ハリスンも存分に味わうことができます。
このアルバムの演奏の素晴らしさを挙げていくとキリがなくなるのでこの辺にしておきすが、では、なぜこれほどまでに素晴らしい演奏がたくさん生まれたのでしょうか。
その最たる理由は、楽曲が良いからに他ならないと思います。
これは僕もミュージシャンの端くれとして、実感としてわかっているつもりのことなのですが、曲が良いとプレイヤーの想像力もかき立てられ、良いアイデアが次から次へと自然と生まれてきます。そしてそれが良い演奏に繋がっていきます。良い演奏は、良いアイデア、良いフレージングがあってこそのものなのです。
また、信頼のおける“仲間”とも言えるミュージシャンが集まってのレコーディングセッションだったということも大きな理由のひとつだと思います。演奏は、人との関係性やそのセッションの雰囲気に大きく影響されます。ジョージのユーモラスな人柄も、セッションの雰囲気をきっとより良いものにしたのでしょう。僕はこのアルバムを聴いていると、そのレコーディングセッションの良い雰囲気まで伝わってくるような気がして、さらに好きになっていくのです。
そんな音の持つ雰囲気も、アナログだからこそ、より感じられるものなのです。