【インタビュー】J、ライヴ映像作に「手を伸ばせば仲間がいる特別な空間」

瞬間瞬間を燃やし尽くすように生きてきたJが不変のロックを鳴らすべく作り上げた10枚目のアルバム『eternal flames』は全国各地に消えない炎を放つことになった。その胸を焦がす熱いライヴをパッケージしたライヴ&ドキュメント映像作品『CRAZY CRAZY V -The eternal flames-』が3月16日にリリースされる。
◆J 画像
初日からこれまでに経験したことがない熱さが会場に渦巻いていたというツアーでJが掴み取ったものとは? 映像の中の「自分のやりたいことは1stアルバム『PYROMANIA』で終わっている」という衝撃発言は何を意味しているのか? おそらく日本ロックシーンの中で最も憧れられているベーシストのひとりであるJの生き方、自らのやり方で道を切り開いてきたミュージシャンの姿勢と今を、ライヴ&ドキュメント映像作品から浮き彫りにする。
◆ ◆ ◆
■バンドの危機が水面下であった中で
■借りてきた服を着るみたいなアルバムを作る気はなかった
──2015年10月10日に赤坂BLITZで開催されたライヴの模様を中心に収録した『CRAZY CRAZY』シリーズ5作目の映像作品『CRAZT CRAZY V -The eternal flames-』がリリースされますが、10作目となるアルバム『eternal flames』をひっさげて廻ったツアーで見えた景色というのは?
J:『eternal flames』はすごく気合いを入れて作ったアルバムだったので、自分が重ねてきたその時間も全て内包した上で、今の俺をぶつけるつもりでツアーに挑んだんだけど、本当に今回は初日の1曲目から今まで味わったことがないテンションで会場が迎えてくれたんですよ。初日っていい意味でも悪い意味でも固かったりするし、探っていく部分もあるじゃないですか。なのに、まるで何ヵ所も廻ってきたような感覚があって。あのアルバムの熱量を、観に来てくれたみんなも感じてくれたんだなって。新曲たちが何年も演奏している曲のようにメニューの中に溶け込んでいくのを感じて、この場所に辿り着くために今まで貫き通してきたんじゃないかとも思ったし、だからこそ、このツアーでさらにその思いを押し上げていきたいって。勢いだけではなく、奥行き、広さ、強さ、そういうものを全て手にしたいし、バンドであることを見せたい。そういう想いが強かったんですけど、初日からそれを受け入れてくれる空間が広がっていて。
──予想以上の景色が目の前に。
J:そう。それは自分が望んでいたものだった。「このツアー、最後まで行ったらどうなるかわからないね」って言いながら廻っていったんだけど、そんな中で迎えたファイナルの赤坂BLITZの映像が収録されています。
 ──映像作品には観ていて思わず前のめりになる熱いライヴはもちろん、インタビュー映像も多く挟みこまれていますよね。それは今の自身の気持ちを言葉で残しておきたかったからなんですか?
──映像作品には観ていて思わず前のめりになる熱いライヴはもちろん、インタビュー映像も多く挟みこまれていますよね。それは今の自身の気持ちを言葉で残しておきたかったからなんですか?J:基本的に前回の作品もライヴ、インタビュー、ドキュメンタリーを軸に構成されているんだけど、インタビューをどの程度使うかは監督にある程度任せてるんですよ。たぶん、俺が話したことが今回の作品に必要だったから割合が増えたんだと捉えていますけど。
──そのインタビューの中で、「自分がやりたかったことは1stアルバム『PYROMANIA』(1997年)で終わっている」と発言していることには驚きました。最新アルバム『eternal flames』は1stを作った時の感覚に近かったということですが、これまでだってエネルギッシュなロックアルバムをたくさん生み出してきたわけですよね。
J:1stアルバム『PYROMANIA』を作ったときの想いは今だにハッキリ覚えているんですよ。LUNA SEAが活動を休止している期間に作ったアルバムで、バンドをやる中で自分に芽生えていた想い……ポジティヴなものもネガティヴなものも含めて。そういう気持ちがなかったら、ソロには向かわなかったわけで、休止期間だから出そうということではなかった。自分の主義主張がなかったらソロアルバムなんか作る必要はないし、そのときに打ち出したい俺の音楽が存在していたのは事実なんですよね。“こういう熱を持ったこういう響きの音楽があったから、俺っていうヤツが生まれたんだよ”っていう自分の存在理由を明確にする必要があると思っていたし、それを表現しない未来は想像がつかなかった。だから、死ぬ気で向かっていったよね。
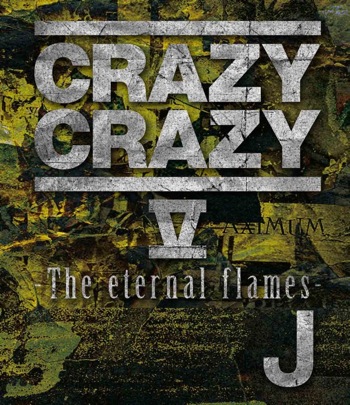 ──この1枚で終わってもいいと思ったぐらいに?
──この1枚で終わってもいいと思ったぐらいに?J:当然。俺が聴いてきたバンドや音楽はそれぐらいの熱量を持っているものばかりだったからね。バンドの危機が水面下であった中で“自分にとって音楽って何だろう”って考えたし、昨日今日、借りてきた洋服を着るみたいなテンションのアルバムを作る気はなかった。だから、曲も音も1つ1つ作っては壊し、作っては壊し、自問自答していた自分を今でも覚えているし、名刺はふたつ要らないっていうことだよね。
──Jそのものを表現した名刺代わりのアルバムが『PYROMANIA』だったということですよね。
J:そう。それ以上でもそれ以下でもないものを作れたら最高だなと思っていたから。あのアルバムでやろうとしたこと、やれたこと、やれなかったことも全部含めて俺の世界はあそこで始まって、そしてある意味終わっている。だから、『PYROMANIA』を聴いてくれたら俺がどんなヤツかは理解してもらえると思う。
──確かにそうですよね。
J:そういう意味では、それ以降の作品たちは『PYROMANIA』の“あの曲のあの部分はこういうことだったんだよ”って紐解いていくような作品だったのかなと思うときもある。新しくもなければ古くもなっていない。つまり、それぐらい絶対的な音、自分が一生賭けて鳴らしたい音を1stアルバムに入れたかったんだよね。それが出来たとも思っているし、今でも本当に愛おしいアルバムだしね。
◆インタビュー(2)へ
この記事の関連情報
【ライヴレポート】J、2023年最後のソロ公演に真の強さ「みんなは俺の人生の生き証人」
J、右足骨折でも激しいステージ「ウソみたいな本当の話があります」
<イナズマロック フェス>、西川貴教のステージにASCA、J(LUNA SEA)がゲスト出演
【ライヴレポート】J、恒例バースデイ公演で新曲披露も「大好きな音楽を求めてまだまだ全速力で突っ走っていける」
【ライヴレポート】J、3年3ヵ月ぶり声出し解禁+夏のツアー開催発表も「新たなフェーズに行きましょう!」
【インタビュー】J「自分が音楽をやる前から存在しているプレベというものは、果たしてなんなんだ?」
【レポート】J、ソロ25周年を締めくくるカウントダウンライヴで2023年春公演開催発表も
フェンダー、LUNA SEA・Jの日本製シグネイチャーベース『MADE IN JAPAN J PRECISION BASS』を11/25に発売
J、バースデーライヴを開催。2022年ラストを飾る年末2days公演も決定