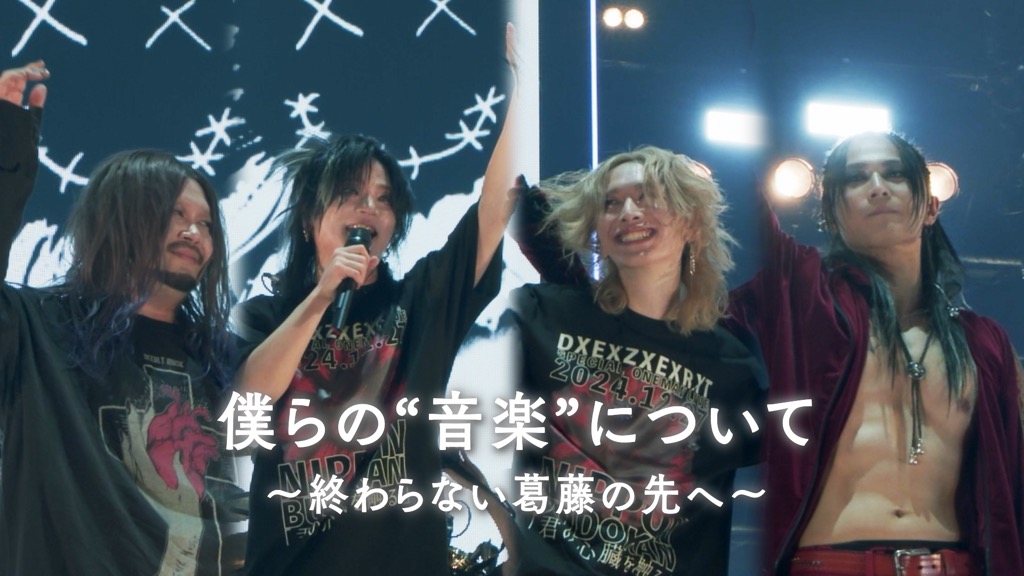【対談連載】ASH DA HEROの“TALKING BLUES” 第1回ゲスト:Ken [L’Arc-en-Ciel]

■自分の立てたハードルに届かないから
■届くようにするデビュー2年目だったと思う──Ken
──<BEAST PARTY>の会話から始まって、<PARTY ZOO><MIDNIGHT PARTY ZOO>、そして<BABIES NIGHT 2016 〜After Party〜>と、わずか4〜5回ですけど、この半年の間に濃密な時間を過ごしているわけですね。以降、ステージのみならず、プライベートでもご一緒する機会があったとか?
Ken:今年の新年会かな。AKiが「やりたい」って言い出して。「じゃあ、やろう!」って2日前にOKの返事を返したのね(笑)。
──学生の飲み会ノリに近いものがありますが(笑)。
Ken:ははは。そうしたら、AKiが動いてくれて。みんなで肉食べて、濃いめのお酒を飲んで。
ASH:すごくたくさんのミュージシャンが集まって、ホントに楽しかったですね。このままみんなでセッションしたら楽しいだろうなっていう空気もあって、この感触が<PARTY ZOO>なんだなっていう。そこで音楽の話をしたりとか。

|
| ▲ASH DA HERO |
──フラットな感覚での付き合いだと思うんですが、世代的には異なるわけで。ASHがKenさんを認識したのは幼少時代でしょうし、それもテレビ画面の向こう側の人だったわけですよね?
ASH:それはやっぱり小学校のときですよ。
Ken:……小学校(笑)。
ASH:テレビで観たのが「HONEY」だったんですけど、少女漫画の世界から飛び出してきたかのような印象でしたよね。“なに!? この二次元感!”って。で、僕らの世代ってタバコを吸いながらギターを弾く人を、Kenさん以外で観たことがなかったから、それは衝撃でしたね。
──確かに、テレビでもライヴでもタバコを吸いながらっていうのが、あのときのKenさんのある種のトレードマークであり、そのロックな感覚にヤラレた男子が大勢いたと思います。
Ken:最初は演奏中にタバコを吸うっていうことはなかったんだけど、吸いたくなるじゃん? で、吸ってもいいんじゃないかなって。吸ってみたら誰もなにも言わないし、吸ってもいいんだ、じゃ、吸っとこっていう順番だったの。
ASH:バンド内でのキャラクターもさまざまだったし、そのなかでもKenさんはシブいギターヒーローというか。今思えばチョーキングとかが印象深くて。チョーキングをしながら身体をのけ反らせたり、ギターを持ち上げたりっていう姿に、クールで寡黙なイメージを持っていたんです。だから、<BEAST PARTY>で、「いい天気やねー!」って気さくに声をかけていただいて、すごくいい意味でのギャップを感じたんですけど。
──テレビで観ていた二次元の人と、カーティス・メイフィールドの話題で急激に近づいたわけですもんね。
ASH:そう。音楽って人と人を一気に引き寄せる力があるんです。おっしゃるとおり引き合わせてくれたのはカーティスだし、昔の音楽家の話で、世代とか肩書きとかを超えることができたというか、バイパスになってくれた。
──デビュー1年目には多くの出会いがあって、そのひとつひとつがASHの今にとって大きなものになっているという。
ASH:<BEAST PARTY>も<PARTY ZOO>も本当に大きな出会いでしたね。昨年末に僕はデビュー2年目を迎えたんですけど、フレッシュさは失わずに、新人という枠を超える1年にしたいと思っているんです。日本にソロロックシンガーって少なくなってきているじゃないですか。でも、そのラインにしっかり乗って、近い世代のミュージシャンのなかでトップを目指す必要があるなっていうことを、今、すごく感じているところで。Kenさんはデビュー2年目のときってどんなことを考えていたんですか?
Ken:もう20数年前の話だから、正直なところ覚えてないんだけど。さっきから話に出ている“ヴァイブス”って、個人のなかにもあると思うんだ。“ここまでヴァイブスが上がったときに見える景色”っていうもの……音を出さずに頭でイメージできる景色があって。それがギターを持ったときに現実に引き戻されちゃうときもあるんだよね。そのイメージを崩す音が出ちゃうから。だけど、イメージをブーストさせる音が出るときもあるわけ。これが腹立つんだよ。常に自分の思った景色が出るようになりたいわけ。
ASH:イメージを音で具現化したいという。
Ken:そうそう。逆もあって、先にギターを弾いて、そこから風景が広がることもある。たとえば、目で見えちゃってる景色はすごく奥行きが狭いんだけど、目をつむった瞬間にどこまでも奥行きが広がっていくっていう。音色もそうだし、弾き方もそうだし、コードワークなのか、曲なのか。そのイメージのすべてが出るようになったら気持ちいいっていう動機のもと、動いてた。
──それが2年目くらいのことですか?
Ken:デビュー1年目に『Tierra』(1994年7月発表)っていうアルバムを出して。その次が『heavenly』(1995年9月発表)なんだけど、1年目も2年目もそれを目指して動いてたと思う、ただただそれだけ。だから、自分の立てたハードルに届かないから、届くようにする2年目だったと思う。
ASH:あぁー、Kenさんにもそういうものを抱えている時期があったんですね。
Ken:今でもそうだよ。
ASH:そうなんですね。その頭のなかに生まれたインスピレーションの泉の水をすくって、その水がどんな色をしているのか、どんな煌めきをするのかっていうのを確認して、それをいとも簡単に表現できてしまうようなギタリストだなっていうのがKenさんのイメージだから、ちょっと驚きました。
Ken:ASHの表現を借りれば、“何色かな”って確認した瞬間に、見えなくなるの。そこにあるのに確認したら無くなる。そうしたら、“あ、すくっちゃダメなんだ”とか。
ASH:なるほど。
Ken:自分がまだ中学生くらいのときに、部屋の電気を消して、鳴るギターの音に身を委ねて、広がる世界を見ようとしていたんだよね。静けさのなか一人で集中して弾くと、そのモードに入っていける。瞑想に近いのかな。そこで、ちょっとでも“なにか見たい”と思うと、パンッって一気に自分の部屋に戻っちゃうんだよ。
ASH:僕も、部屋を真っ暗にして、点いている明かりはMTRのLEDランプだけっていう状態で歌を録ったことがあるんです。そのランプがだんだんランプじゃなくなっていくような感覚をおぼえたことがあるんですけど。
Ken:そうそう。光じゃないものに見えたり、遠くのなにかに見えたり。
ASH:脳内麻酔みたいなものが出ているんでしょうね。
Ken:それが気持ちいいから、自分が気持ちよくなるためにそのモードに入りたくて。で、それはずっとそう。他に付随するものはあるんだけど、基本はそこなんだよね。自分のピッキングが甘いときに“うわっ、現実に戻った”みたいなのがイヤだから、指の使い方を試行錯誤したり。
ASH:ご自身が頭のなかに描いた音の小宇宙を身にまとえるようになったそれ以降があって。その音世界に身を委ねながらパフォーマンスする姿を僕はテレビで見ていたんですよね。だから僕の小さい頃のKenさんに対するイメージ……タバコをくわえながらチョーキングに身を委ねている姿って、そういうことだったのかもしれない。なんか、すごくつながりました。
Ken:照明がチカチカしていることとか気にせず、そこにいけるようになった頃かもしれないね。そういう意味では何年目っていう差がないんだけど。
──おっしゃられたように、今も継続しているものということですよね。
Ken:アマチュアの時代から曲をいっぱい書いている人は、それが蓄積されていろんな場面で注ぎ込めるかもしれないけど、俺はあんまり曲を書かないほうでね。たとえば2作目のときは2作目用に書いているから、1作目とはちょっとマインドが変わっているということがある。