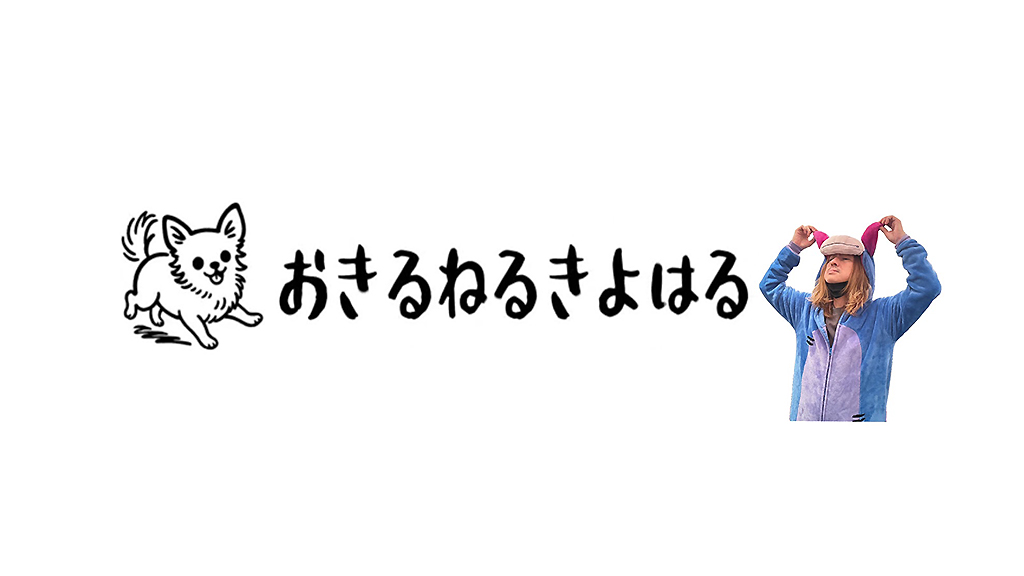【インタビュー<前編>】清春、『エレジー』完成「ダークさとか、今までやってきたことは剥せない」

■そもそも音楽って文化系のはずだけど
■昨今どうしても体育会系を求められがち
──確かに、絵にたとえて言うなら、あのマウントレーニアホールという劇場で、清春さんが即興的に描いている感じはしましたけどね。
清春:こっちの<エレジー>のほうは、限りなく形がないんだよね。もちろん、バンドサウンドのほうも好きで始めたので。ただ、バンドサウンドを構成していく、ギター、ベース、ドラム。あとはキーボードとかサンプリングなんかが入ってたりすると、やっぱ歌の自由度は減るんだ。
──その形態に縛られてしまうところもある?
清春:まあ、ルールが増えるっていう。コードとかリズムとか音色とか。だから、それはそれで、そのなかでのベストの響きを達成していくと、美しいものになるんですけどね。シンガーとしては、セッションをしてる感覚は楽しめると思うんですよ。まあ、4ピースとか3ピースのなかにいながら、ギターとハーモニーできてるとか、ベースと寄り添えてるとか。ドラムとすごい躍動感が似てるとか。そういうのプラス、ギターとベース、ベースとドラムっていう組み合わせによって、ぐんぐん上がってくるのが良い面。でも、そうなるとフリーキーではないっていうのが悪い面。それが今のところ出てる長年の結果なんですけどね。
──なるほど。
清春:なんか、それぐらいできちゃう人だったらいいんですよ。ジャズのバンドとかだったらできちゃうのかもしれないけど、ロックに関していうとなかなかだよね。今やクリックなんて当たり前だし、それがすごい気持ちいい作用を及ぼす時もたくさんあるんだけど、やっぱり、テンポとコード、あと音量。これで支配されることが多い。ヴォーカリストにとってはフリーキーではない場面もたまにある。この<エレジー>に関していうと、歌で引っ張るっていうか、歌についてくるところ。まあ、今回は、ギター2人いますけど。すごく難しいんですよ。読者の方がやってみてくれたら、わかるんだけどなぁ(笑)。
──ははは! 確かに。
清春:僕の今回のやつって、ディープなことを言い出すと、なんとでも言えるんですけど、聴く人ってもっと浅い段階で選んじゃうから。早い段階というか。“あ、このバンド激しくないんだ”とか“バンド風じゃないんだ”とか。“暗いんだ”とか“静かなんだ”とか。なんなら、“ソロなんだ”や“バンドなんだ”で選んじゃう。だから、すごく惜しいなって思うんですよね。
──そこのゾーンに一歩入るか入らないかで違ってくるわけですね。
清春:うん。すごい違う。JAPANっていうバンドがいて、すごいカッコいいんだけど、デヴィッド・シルヴィアンのソロも、ものすごく芸術的で繊細なんですよね。それぐらいの差だったらいい。JAPANとデヴィッド・シルヴィアンだったら両方ともアートだからいいんだけど、スポーツとアートの差っていうか。それくらいの隔たりがあると思うんですよね。僕がやってきたことで言うと体育会系と文化系ぐらいの違いは結構あって。まあ、そもそも音楽って、ホントは文化系のはずなんですけど。どうしても体育会系を求められがちな昨今ですからね。
──バンドのほうが体育会系に寄っているということですか?
清春:そう。まあ、たとえばさ、体育会系の部活だと、ユニフォームがあるじゃない、同じジャージとか。でも、文化系は学生服じゃないですか。確かに体育会系は動きやすいし、みんなお揃いで気持ちいいんだけど、普段制服着てる人がジャージとかユニフォームに着替えても、その先はないんですよ。熱くなって、裸になるしかない。だけど、文化系は制服で一人で制服のままそれを突き詰めてやってるのって、何者にも変われる可能性を秘めてるなと思うんですよね。僕も勉強しなかったので、どっちかっていうと文化系は苦手なんだけど、音楽を選んだ時点で、要はスポーツではないわけ。ロックの激しくて、ワーっていう部分も大好きなんですけど、ソロでやってくことに関していうと、これがすごく正しい表現方法の一つなんじゃないかなとは思います。イギー・ポップみたいに、ソロでも激しい場合とかはあるんだけどさ。

──なるほど。しっかり聴いてみればわかるように、『エレジー』は決しておとなしい作品ではないじゃないですか。
清春:うーん。みんな、そこまで理解して聴いてくれるかな(笑)? 一聴して、“暗い”とか“おとなしい”とか“地味”とか“静か”とか、それで終わる人は日本にはすごく多いよ。いろんなアーティストの普通のアルバムがあるけど、アコースティック的なアルバムはなぜか日本では売れないんですよね。
──メインのものに比べてちょっと下のもの、みたいな認識はあるのかも。
清春:うん。音が少なくて損してる、みたいな。僕もアコースティック・アルバム聴かない場合が多いんですよ。ただ、さっきも言ったけど、今回のは、よく音楽知ってる人には、“アコースティック・アルバムではない”って言ってるんですね。よく音楽知らない人には“アコースティック・アルバムみたいなやつです”って。例えばマリリン・マンソンのアコースティック・アルバムとかって、あんまり聴きたくないじゃないですか。
──まあ、ボーナス・トラック的にはあるかもしれないですけどね。
清春:そういう秘められたものっていうのは、カッコいいんだけどね。しかしバンド出身のソロシンガーっていうのは難しいね。始めからこれでデビューしてれば、もう、足し算しかないじゃないですか。
──“昔ああいうことをやっていた人が今こういうことをやってる”みたいな驚きは、大きいのかもしれないですね。
清春:そうそう。井上陽水さんとかだったら、最初はフォークで、いろんなことを足していっても、“あ。今回はゴージャスだな”ってなるんですけど。でも、すぐに弾き語りに戻れるじゃない。それが特別じゃないっていうか。僕とかはやっぱりそれの逆なんで。
──そこが面白いところでもありますね。
清春:うーん。それがみんなにわかるかなあ(笑) ファンの人もだんだん大人になってきてて、人生のわびさびがわかるようになってらっしゃると思うんで、わかってくれてるのかなって感じはする。ただまあ、さすがに僕も49歳なんで、“似合ってる”と思いますけどね。普通に考えたら、年齢的に似合ってるというか。
──シンプルだからこそ伝わる本質ってあると思うんですよ。そこの部分が非常にうまくコントロールされているなと思いまして。
清春:ただ、僕が身に付けてきたというか、もう身に付いちゃってるというか、イメージ的に剥せないものなのかもしれない。ダークさというか、暗さというか。“黒夢”っていうバンド名や、大昔やった首吊りパフォーマンスとかでも、決して明るいほうではなかったじゃないですか(笑)。結果的に、それが自然によく出てますね。意識しても、今までやってきたことは剥せない。よりこの感じに合ってますね。
──結局、芯の部分は変わらずに、より深くなっていっているということなんでしょうか?
清春:現状も、いろんなことが足されて足されて、清春という人間が形成されていってるんだと思うけどね。なんかすごくね、“無理してない”んだと思うんですよね。すごく無理して違う音楽やって出口へ向かえる人っているけど、今自分のやってることというのは、その逆で、すごく楽してるなと思いますね。余計なことをしないというか。かつ、音楽的なチャレンジはしている、と。好きなことだけしかやってないっていう感じは客観的にしますね。こういう人がいたら、“ああ、なるほど”って僕も思います。