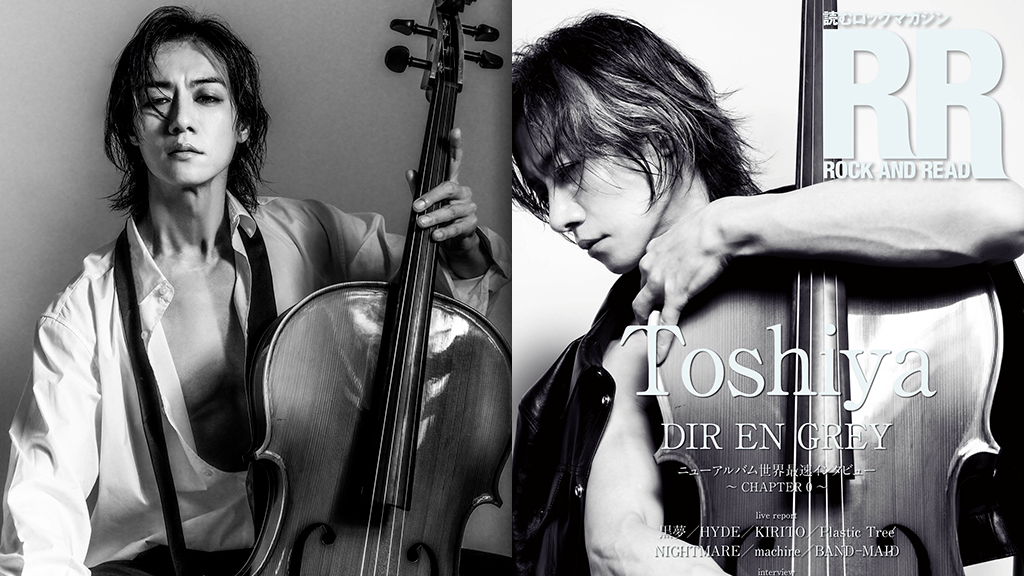【インタビュー】DIR EN GREY、結成20周年のシングル『人間を被る』

DIR EN GREYが2016年7月の『詩踏み』以来、実に1年9ヶ月ぶりとなる29thシングル『人間を被る』をリリースした。結成20周年を経て最初に発表されるこのシングルで、バンドはどこへ向かおうとしているのか。また、2014年12月発売の『ARCHE』以来となるニューアルバムの行方は。メンバーのDie(Gt)とShinya(Dr)に、近況や新作についてじっくり聞いた。
■昔はどんどん付け足して延ばしてっていう感じなのに対して
■今はいかに中に凝縮させて聴かせられるかという方向性
──シングルとしては前作『詩踏み』からもう2年近く経ちますね。
Die(Gt):そうですね。まあ、ここのところライブばっかりやっていましたから(笑)。2017年はツアーが日常化してましたし。当たり前のように、ひとつのツアーが終わったら次のツアーの曲をまた覚え直してっていう、その作業の繰り返しでしたからね。
──実際、ツアーごとに過去のアルバムを振り返ることになるわけですよね。そこでDIR EN GREYというバンドの20年にわたる歴史を、改めて曲で実感する瞬間もあったのかなと思うんですが?
Die:やっぱり、今から一番遠いアルバムが、現在の自分たちとは曲の作りやタイム感が全然違っていて。昔はまだ単純だったというか、どんどん付け足して延ばしてっていう感じなのに対して、今はすごくコンパクトで、いかに中に凝縮させて聴かせられるかという方向性。ライブをするときに最近の自分たちの曲と過去のアルバムの曲が混ざることですごく違いを感じました。
Shinya(Dr):僕も若いときはいろいろ詰め込みたくなる時期があったので、当時の曲を今やってみるとすごく大変だなと思いました。

▲『人間を被る』【完全生産限定盤】

▲『人間を被る』【初回生産限定盤】

▲『人間を被る』【通常盤】
──実際、どのアルバムのツアーが一番大変でしたか?
Die:『MACABRE』(2000年発売の2ndアルバム)ですかね。よく覚えているんですけど、ツアー初日が確か高知で。リリース当時の演出とかも再現してやるんですけど、椅子のあるホール会場だったので、お客さんもステージをじっくり観るという雰囲気だったんです。そこも影響してか、または1本目だからといのもあってか、ライブをしていてもなかなか熱が上がっていかなくて。特にツアー1本目は自分の立ち位置で黙々と演奏するだけみたいな感じだったので、さすがに「あれ、当時はどうやっていたんだっけ?」と考えましたね。
──そこはどうやって乗り越えたんですか?
Die:ツアーを続けるうちに自然と自分たちが曲に馴染んでいったのかな。2000年の曲なので、さすがにちょっと遠すぎて、なんだかコピーしているというか。まったく別モノという感覚があったので、それがライブを重ねることによって少しずつ過去の感覚を思い出せたんですかね。
──なるほど。Shinyaさんはツアーを振り返って、「これは難しかったな」という作品のツアーはありますか?
Shinya:音数の多い『MACABRE』とか『鬼葬』(2002年発売の3rdアルバム)とかは、今プレイするには難しかったかな。でも、曲を思い返すのは全然苦じゃなくて、逆にわりと最近の曲のほうが思い返すのに時間がかかって。構成も難しいですしね。

▲Die
──思えば、アルバムごとにこれだけサウンドやスタイルが変化しているバンドというのも、日本の音楽シーンの中でもかなり珍しいと思うんです。それこそ、1枚目『GAUZE』(1999年発売)と最新作『ARCHE』(2014年)を比較したら……。
Die:完全に別のバンドですよね(笑)。今年の頭にベストアルバム(『VESTIGE OF SCRATCHES』)を出しましたけど、聴き返すと「これ、何バンドか曲が混ざってるやろ?」って感じますものね。ひとつのバンドのアルバムだと思えないぐらいに曲のバリエーションが広くて、音も声も違いますし。
──実際、ギターという観点ではこの20年で、プレイとの向き合い方はどのように変化しましたか?
Die:自分の中で極端に変わってきたのって、やっぱり2011年の『DUM SPIRO SPERO』ぐらいからで。基本的にギターが二人ともユニゾンで弾くことが多くなって、そこを軸に曲を作っていくことがすごく増えて、それが今も続いている感じなんです。それ以前はわりと二人ともフリーなスタイルでやっていたんですけど、そこの違いが今は大きいのかなと、単純に思いますね。
──僕の印象ですけど、2000年代末以降はリフでグイグイ引っ張りつつ、音で塊を作るようなアンサンブルが増えているイメージがありまして。
Die:うん、そうですね。ギター自体もその頃から7弦ギターがメインになってきたので、バンドサウンドの作り方自体がやっぱり変わってくるんですよね。ドラムを基準に音を積み上げていくんですけど、ギターの低音自体がどんどん低くなっているから、どこにベースの位置を持ってきたらいいのかでToshiyaも悩んだと思うし、それによってベースのプレイスタイルもスラップメインになってアタックを出す方向に変わっていった。それが2000年代末ぐらいからなのかな。

▲京
──そういうとき、Shinyaさんはプレイのみならず、ドラムのチューニングも変えていくわけですか?
Shinya:ですね。やっぱりドラムも低いチューニングが求められるようになりますし。それによって、プレイもアルバムごとにいろいろ変わってくるんです。
──改めて20年という歳月って、普通に考えると子供が生まれて成人するぐらいの期間ですよね。
Die:そうですよね。結成20年っていうのは、イコール、俺たちが東京に出てきて20年ということなんです。だから、地元よりも東京にいる期間のほうが長くなりましたし、トータルで考えても家族といるよりメンバーと一緒にいた時間のほうが長いわけで。だから、不思議な感覚ですね。
──20年も一緒にいると、メンバーとの関係性も変わってくるわけですよね?
Die:なんていうのかな……普段から五人がずっと一緒にいる、という仲よしこよしな感じではないんですけど、それぞれ程よい距離感を保ちつつ。東京に出てきた頃は周りにこの五人しか知ってる人がいないので、常に五人で行動していましたけど、ここ数年はこれが自分たちなりの良い距離感なのかなと思います。
Shinya:うん。だから20年も続いているんでしょうね。
──それと、特にここ数年で変わったこと、新しいなと思うことが、DieさんやShinyaさん、それに京さんによるバンド外での音楽活動かなと。
Die:そうかもしれないですね。自分はDECAYSをやっていますけど、DIR EN GREYとはまったく立ち位置が違うところでやっていますし、刺激しかないですよね。しかも、頑張らないといけないことも多くて、それもすごく自分にとってもよかったなと思いますし。DECAYSをやったことによって、今更なんですけども、DIR EN GREYでギターを弾いている自分が自信を持って「俺はここなんだな」っていうことを余計に感じられたというか。DIR EN GREYで上手(かみて)に立ってギターを弾くのが俺のポジションなんだなっていうことに、一回外に出てやってみて気づかされたんです。だから、外で活動していも比較対象はDIR EN GREYだし、ちょっと俯瞰で見るとすごいんやなって思いました。
──具体的に、どういうところをすごいと感じましたか?
Die:こういう曲を作れないわけですよ。上辺だけ、こういう曲調でシャウトしてとか、そういうことじゃない。それって20年の歴史があるからの重みであって、結成して1、2年でそこまで中身のあるものっていうのは、やっぱりできないですよね。音楽性やクオリティという面では、この五人だからできることなんだなと思って。そこに気づけたという意味でも、やってよかったなと思います。
──Shinyaさんもドラマーとしていろんなアーティストとセッションするほか、2017年にはSERAPHというプロジェクトも立ち上げました。
Shinya:単純に自分がいろんなプレイヤーと合わせることができて、すごく良い経験になって勉強になりましたし、その経験が確実にDIR EN GREYに生かされていると思ってます。