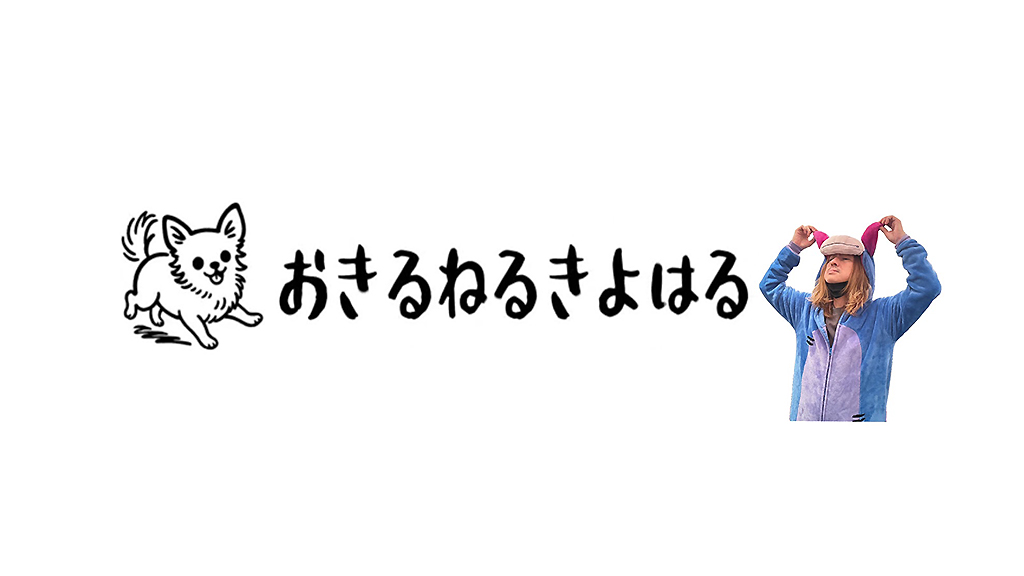【インタビュー】清春、“化粧とロックンロール”を掲げたアルバムに破壊と創造「究極、オケはいらない」

■“地図の絵”を実際に観たら
■凹凸感や細かさ……物凄かった
──その“やまなみ工房”は、知的障害や精神疾患を抱えた入所者が、快適な環境でズバ抜けた芸術的感性に溢れたアート活動を継続できるようにサポートしている場所だとか。今回の一連のアートワークが発表された時も、非常に意表を突かれました。これら印象的な絵は、グアナファトの街並みの色に合わせて、探し当てたんですか?
清春:いや、全然。昨年末、やまなみ工房に行った時に知的障害者の皆さんに会わせてもらって、作品を描いてる様子を見てたんだけど、“おお! すげー!”っていう絵が何点かあったんですよね。やまなみ工房のドキュメンタリー映画『地蔵とリビドー』を作ってるクリエイティヴディレクターの笠谷(圭見)さんは元々、広告代理店に勤めてる人だけど、ここの写真集やホームページも手掛けてて。“地図の絵”を実際に観たら、その映像や画像ではわからなかった凹凸感や細かさがあって、物凄かった。それがたまたまグアナファトの街に似てたんです。ちょうどミュージックビデオのラフが出来た頃のことで、まだ景色を覚えてる状態だったから、驚きました。

▲10thアルバム『JAPANESE MENU / DISTORTION 10』通常盤CDは9種類のチェンジングジャケット仕様
──すべては偶然の出会いだったんですね。
清春:そう。それに“JAPANESE MENU”っていう言葉にも合ってたんですよ。アルバムで使用してるんだけど、地図と日本語表記の絵に“これ、まさにJAPANESE MENUだな”って感じた。
──つまり、清春さんの頭の中にあったコンセプトをやまなみ工房の方々にお伝えして描いてもらったわけではない?
清春:うん、初めからそういう作品だった。やまなみ工房の在籍者は80人ぐらいらしいんですけど、僕が会ったのは30人ぐらい。なかには何もせずに寝転がってる人もいましたし、作品を作るところまでいってない人もいた。最初は壮絶な世界というか、怖いのかなって想像してた部分もあったんだけど、近くで声をかけたら、皆さんすごくチャーミングで。だから……この絵とコラボレーションしたのは、本当にたまたま。偶然です。
──そんなことってあるんですね。
清春:受けた感銘というか、共鳴みたいなところはあるんですよ。じゃないと、一緒に何かをやりたいとは思わなかっただろうから。やまなみ工房は、日本のアール・ブリュットやアウトサイダー・アート (※既存の美術や文化潮流とは異なる文脈で制作された芸術作品)を輩出しているところで、ああいう作品を作ってる施設のなかでは、一番理想的とされているらしくて。彼らが描いた絵を洋服にしてるブランドがあるんだけど、そのブランドの服を僕は知らずに撮影で着てたんだよね。その何年か後に、やまなみ工房から“ライヴをしてほしい”っていうオファーがきたんだけど、調べてみたらそういうことだった。やまなみ工房でライヴする時はギャラリーがライヴハウスになるんだけど、そのギャラリーにあった絵もとにかくすごい。僕らには人と会話したり、買い物に行ったり、仕事する能力があるじゃないですか。でも、彼らにはそういう能力が少ないぶん、違う能力があるんだよね。
──サヴァン症候群のような。
清春:うん。僕は福祉のことはわからないし、それに重きを置くのは自分の役割ではないと思ってて。簡単に言うと、すごくカッコいい絵が街で売ってて「この絵、ジャケットに使っていい?」っていう。やまなみ工房の作品を今より少しでも有名にしたい。ドキュメンタリー映画『地蔵とリビドー』を、笠谷さんは明るい作品にはしなかった。普通は明るくして世に出すと思うんだけどね。
──興味深いお話です。
清春:僕らがやまなみ工房を訪れた時、描いてる本人たちや絵に対してもだけど、同時にそれをパッケージにして伝えてる笠谷さんに感銘を受けたんです。いつの間にか僕がその服を着てたように、ウチのファンの人が『JAPANESE MENU / DISTORTION 10』の中に好きな曲が出来たとして、それを聴く時、一緒にこのジャケットに思いを馳せるじゃない、“やまなみ工房の芸術なんだ”って。それって素敵なことなのよね。微力ながら僕も、そんなお手伝いをしたい。
──アルバムの具体的な内容についても聞かせてください。曲作りやレコーディングで苦労されたことは?
清春:ありますよ。毎回のことですけど、アレンジャーの三代(堅)さんと僕のやりたいことのズレとか(笑)。
──いやいや(笑)。サウンドとしては今回、基本的にベースレスですか?
清春:そう、「SURVIVE OF VISION」「忘却の空 25th Anniversary Ver.」以外はベースが入ってない。
──ドラムとベースとギターが必要最小限と言われるバンド編成ですが、そこからさらにベースを抜いたシンプルなサウンドの上に、清春さんの歌声が乗っている?
清春:僕が作ったデモテープにはベースは入ってた。でも、今回参考にしてたのはブラック・ピストル・ファイヤー(カナダ出身の2ピースバンド)。
──ガレージロックっぽいサウンドですよね。
清春:その代表的な例はホワイト・ストライプスとかだよね。そんなの世界にはいっぱいあるので、“一回ベースレスでやってみましょう”って三代さんに伝えたんです。
──アレンジの参考としてですね。
清春:でも、最初は僕の意図するのとは違うのが出てくる(笑)。いつも何回かやり直しがあるんだけど、それ以前にまず、僕の言うことへの読解に時間がかかる……“三代さん、なんで必ずおまけが付いてくるんすか?”って(笑)。三代さんとは10枚アルバムを作ってるから、もう15~16年も一緒にやってるんだよね。そうなると、“こういう感じ”とか細かく説明しないもんね。