【コラム】「この世界の片隅で -color-codeの奇跡-」第4話

第4話「スクロール50」
color-codeは言うなれば、あっちこっちに行きたがる色の違う馬が引く馬車みたいなものだった。全速力で突進しようとする赤い馬、ゆっくりゆっくり自分のペースで右に進もうとする緑の馬、立ち止まっては後ろを振り返りながらチンタラと左に進む青い馬。その馬車は双方向から引っ張られガタガタになりながら進む方向を見失い、手綱を引く人がいなくなってしばらく右往左往していた。
本人たちも何をしたらいいかわからないというお手上げ状態の中、彼は静かにその手綱を握った。プロデューサーXである。
彼は以前、某大型事務所でプロデューサーや講師として活躍していた。ガールズグループやダンスボーカルについてのノウハウもあり、マネジメントに関してもいままで関わった誰よりも経験があった。これからプロデュースに入ってくださる方だよと紹介された肩書きを聞いて、わたしたちは「やっと来た。これでわたしたちも立て直せるかもしれない…!」と息巻いた。
結論から言うと、彼とわたしたちは、相性が悪かった。
「完全プロデュース」に一度トラウマがあるわたしたち
vs
「完全プロデュース」するアーティストしかやってきたことのないプロデューサー。
ファイッ!!!!!
プロデューサーXは、わたしたちにまずこう言った。
『言うことだけは一丁前だけど実力も何も無い、ビジュアルも特に飛び抜けてない、人格も破綻したお前たちを俺は根本からぶっ壊す。言うこと聞かずに「わたしたち的には〜」とか言ってんじゃねぇ。お前たちのカッコいい基準なんてどうでもいい。俺は売れる為にcolor-codeをやる』
最初のプロデューサーに見捨てられたのは自分たちに魅力がなかったからだと、わたしたちも薄々感じていた。それはとても辛い現実だったけど、それでも、止まるわけにはいかなかった。
では、どうしたらいい?どこをどう変えたらいい?そんな問いを自分たちに投げかけ続けた沈黙の1年があったから、初めて受けたこんなパワハラ発言も、私たちを本気で売ろうとしてくれている”鬼コーチの愛のムチ”として、真っ向から受け止めた。
しかし、鬼コーチの指導が始まって1年ほどで、わたしたちの頭に徐々に「………?」が浮かび始めた。
Xの特徴として、「深夜にスクロール50回分くらいの長文LINEがくる」というのがある。大阪のライブに車で日帰りで行ったとき、ライブを終えてマネージャーもメンバーもへとへとの車内、深夜1時。
「今日のライブはどうだったか毎回報告しろっつってんだろ」というお叱りがあり、それに対して「これから送ろうとしてたんだよ!!!!」とはもちろん言えない。ひたすら黙々と反省のラインを打つ。そこにさらに食い気味にスクロール50回分が追い討ちされるという形だ。
ちなみにこのプロデューサーX、「現場に来ない」という特徴もある。多忙を極めているらしいのだが、ものの見事にワンマンライブ以外は観に来ない。なので、地方の営業や東京のライブハウスのライブはわたしたちが反省のラインと動画を送り、その文章を読んでのダメ出しがくる、という仕組みだ。
何か間違ってしまった時も、反省して「申し訳ございません」だけでは決して許されない。「それがお前たちの人間としての質だよ。終わってます」と言われ、「はい、申し訳ございません。わたしたちはクズです。人間として終わってると思います」くらい言わなければ、また50スクロールが待っている。もう恐怖だった。LINEは毎回トリプルチェックをして、お客にお札のお釣りを返すマックの店員くらいメンバー同士で一字一句確認しあって、ビクビクしながら送った。いつ地雷を踏むか分からない。最近流行りの地雷系女子の元祖はこのXだとwikipediaにも書いてある。わたしたちは幾度も地雷を踏み散らかし、それまでの自分たちのなけなしのプライドやスタイルを粉々に砕かれた。
それからXは、”真顔でカッコつけ”を心底嫌がった。”真顔でカッコつけ”とはつまり、初期のcolor-codeのようなことである。実力もないしファンもいないわたしたちは、真顔でカッコつけてもサムいだけ、だから、笑って、応援したくなるちょっと綺麗な普通の女の子三人組のcolor-codeとして振る舞うように、というのが、X流color-codeの売り方だった。SNSにアップする写真も、とにかくニコニコして親近感の湧くような笑顔の写真にしろとのお達しを受けた。真顔の写真をアップすると、スクロール50回分LINEでイジられた。それがチクチクとあまりにしつこくて、いつしか「真顔するとメッッッッッッッチャめんどくさい事になる」という恐怖心を植え付けられていた。
「if〜この声が届くなら〜」というバラードをリリースする際のアーティスト写真撮影の時も、「お前ら今日、真顔だったのか?」とキレ気味のLINEが来た。「真顔だったって言ったら怒られるな」とビビったわたしたちは「真顔っていうか、今回めっちゃ笑顔のイメージでは無いかなーと思って、切なめの表情を多く撮りましたけど、ほんのり笑顔も撮りました!」と答えたら、「俺は真顔だったかそうじゃないかって聞いてんだよイエスかノーだろ質問誤魔化すんじゃねぇうぉらああいかああああああぁうあああああああああぁあぁああかああ」(誇張あり)みたいなブチギレをかましてLINEを退会していってしまった。
「つーかさぁ?そんなにキレるなら自分、現場に来ればよくなーい?」と、今ならギャル語で口答えしてしまいそうだが、つまり地雷ポイントは真顔を撮ったことではなく、答え方だった。確かに「何もかも俺のいう通りにしろ」と言われてるのにわたしたちは自分で判断していた。が、状況を踏まえて自分で判断したことにそこまで発狂されるのは、なんか違う、と本能が告げていた。わたしの本能はその日から、LINEのトーク履歴の魚拓をとり始めた。
一方で、衣装もガラッと変わった。今後衣装は、とっつきにくいおしゃれさは要らない、普通に可愛い、綺麗なお姉さんぽい衣装にするようにと指定された。
第一プロデューサーが抜けてから、わたしたちは衣装も完全に自分たちで決めていたし、ワンマンや軽い撮影の衣装は自腹で購入していた。だから、誰かが自分の衣装を決めてくれるなんて、なんというか、久しぶりで、最初はワクワクした。
与えられた衣装は、本当に私服みたいで、たしかに、そこらへんの綺麗なお姉さんたちって感じだった。リアルっちゃリアル。だけど、まこは私服でも派手なのが好きなので、私服の方が衣装みたいだった。似合ってたけど、無理をしていた。わたしとななみは髪の毛も黒にした。以前のcolor-codeを知る人は、三人並んでてもcolor-codeとわからないだろうというくらいの変貌ぶりだった。

あれこれ指定され、禁じられ、かつてはありすぎて困った自由もなくなっていた。何をするにも許可を取る、相談をする必要があった。それは、完全プロデュースの元では当たり前のことだったのだろう。でも、判断を間違えばスクロール50、「ほうれんそう」が至らなければまた、スクロール50。最初怯えていた私たちも、なんか、だんだん腹が立ってきた。理不尽な謝罪もなんどもしていた。そんな言い方しなくてもいいのに、と思うことも幾度もあった。そして、一番はこれだ。
【さんざん大口叩いてきた割には、うちら売れてなくない…?】
Xがコネを使えば余裕で取れると言った地上波タイアップも、大きなライブも、一本も決まっていなかった。受け入れた束縛感に比例して期待が高まっていたからこそ、自分たちのことを棚に上げてそんな疑念が湧いていた。
さて、これだけ言っておいてなんだが、なんだかんだXには、感謝していることの方が多い。パフォーマンスについてのダメ出しはもちろん、メンバー間でのキャラの構築や心構え、スタッフさんへの対応についても教えてくれた。Xが入らなければcolor-codeはもう解散だと言われていた、そんな窮地も救っていただいていた上に、言葉遣いを度外視すれば、頂いた指導は至極真っ当だったと今でも思う。
“自分たちがカッコいいなんて思うな、今のお前たちはクソダサイ。自分には才能がなくて、一人ではなんの魅力もないということを胸に刻め。そうしたら、自然と支えてくれる周りの方への感謝が湧いてくるはずだから。近しい人に愛されない奴が、100万人の人に愛されるわけがない。愛されたかったら、周りの方に感謝、リスペクト、謙虚さ、誠実さを持って接しなさい。”
これらを骨身に叩き込まれたわたしたちは、心持ちから徐々に変わっていくことができた。いつまでも過去の栄光に縋っていてはなにも変われない。たしかにわたしたちは、天才じゃない。三人とも、ずば抜けた何かがあるわけではない。だから、それぞれが必死で磨かなければ光らない。さいたまスーパーアリーナやレディガガといった古びた鎧を脱ぎ捨てて、裸ひとつで一からまたはじめなければ、なにも始まらない、と。
それから、彼との出来事はわたしたちの引き出しを増やしてくれた。感情というのは一時的な、リアルなものである。わたしたちは記憶の引き出しからこういうカケラを引っ張り出して、感情に焚きつける。悔しかった、辛かった、嫌だった、悲しかった…こういう感情を再び燃やして、歌詞を書いた。「マボロシ」「KAGEROU」「THE MARCH」といったcolor-code作詞作曲の楽曲たちは、彼のおかげで誕生したと言っても過言ではない。感謝してもしきれない。
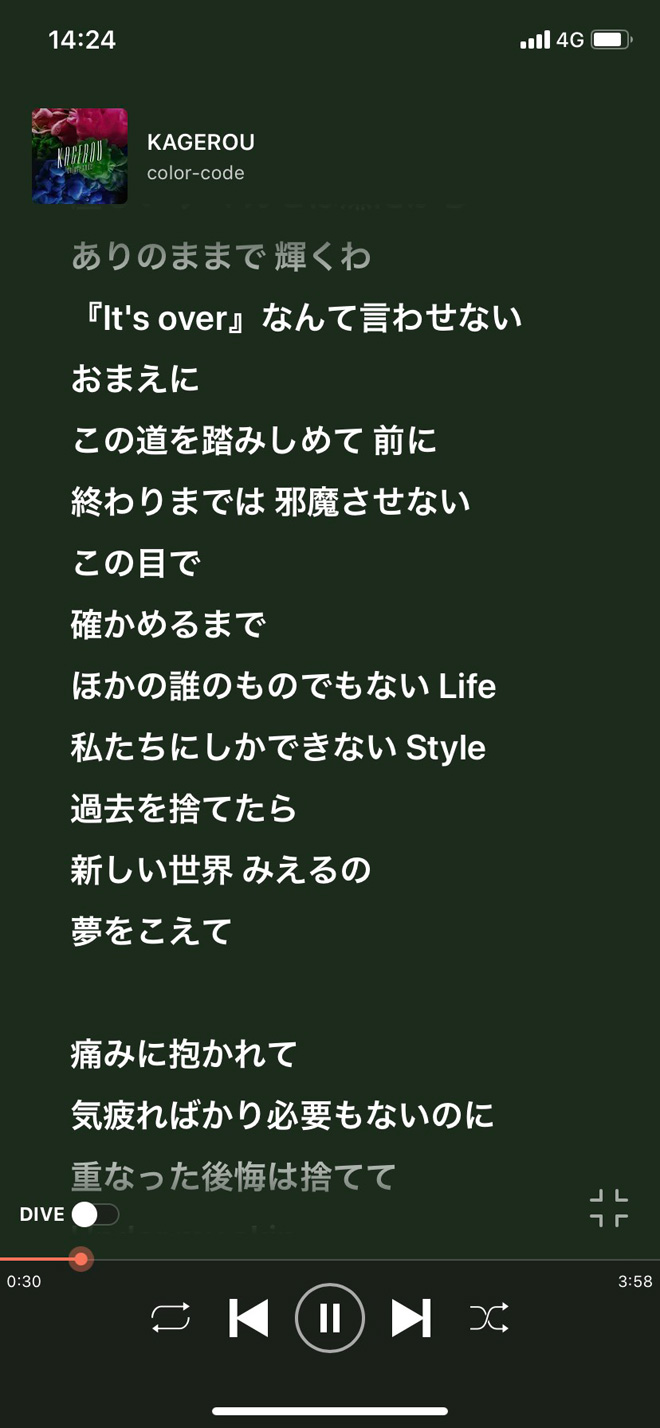
そして、Xがcolor-codeに教えてくれた、もっとも大事なこと。それは、【color-codeは、プロデュースされるの向いてない】と気付けたことだ。
オーディション合格時、三人は、21歳と22歳だった。もうしっかりと自我が構築され、わたしたちは、とにかく、わがままだったのだ。だから三人でも死ぬほどぶつかった。放っておいたら「わたしはこうやりたい」「あなたはそうなんだね、じゃあわたしはこっちいくね」が激しく交錯するようなグループなのだ。そこにもう一人、別の人の意見を入れたら、そりゃあもう、しっちゃかめっちゃかだろう。
それに、完全プロデュースされて売れないと、ついプロデューサーのせいにしたくなってしまう。何年もかけてやってきたことが、人のせいでダメになったと思うとやりきれない。だったら、もう完全に自分たちでやりたい。自分たちで全部やって、これでダメだったら自分たちのせいだ、と、誰のせいにもしないで自分で責任が取れる。諦めもつく。
こうして、いまのcolor-codeの形が出来上がったのだ。
今のわたしたちは、いろいろやってみたけどダメだった、という数々の犠牲があったからこそ、勝ち取った財産だった。Xのおかげだ。
では、感謝してたら何事も有耶無耶に誤魔化して書くべきか?というと、それは違うとわたしは思う。
もう終わったことじゃないか、済んだことじゃないか、蒸し返してごちゃごちゃいうのは大人気ない、と思うだろうか?
それは違う。
前から思っていたけど、「〜するのが大人」とかいう考えはクソだ。
許してやるのが大人、過去のことは水に流すのが大人。そんな大人ならならなくていい。誰かが決めた”大人”など幻だ。自分の中にある怒りややりきれない思いについて、”大人”を振りかざして他人が水に流せなどと言うのは、筋違いにもほどがある。無理に笑い話にするのも、忘れようとするのもやめた方がいい。当人はいくらでも怒っていいし、泣いていいのだ。そうやって自分の感情や記憶を正しく昇華していけるのが、ほんとうの大人だとわたしは思う。わたしたちの中に明確に残る怒りを、誰が水に流すものか。わたしは筆を取り、color-codeは歌にして、昇華すると決めたのだから。
今回はcolor-codeの歴史を書くコラムだ。そこに必要な出来事は余すことなく書き記したい。
誤魔化すんじゃねえとXからも教わった。
だから、書くことにする。この”ファミリー”がなぜ解体したのか、も。
ある日のこと。
朝4:00頃だった。わたしは、夜通しゲームをしていて起きていた。そんな時間には滅多に鳴らないはずのLINEが鳴った。
「(略)makoは今は太ってるんで、『露出度高いと気持ち悪い』と、マネージャーとして事前に突っ込み願います!
だって、一般の方の前で露出度高い服着たがる神経。
少し女性としてどうなんだ?
って話(苦笑)
率直に言って俺には気持ち悪いって印象ですね。
普段着るなら勝手にどうぞですがcolor-codeとしては変態って印象求めてないです。
(中略)
あとストリートそんなにやらなくていいです。
無意味なんで。」原文ママ
冷や汗が出た。
Xはマネージャーへの個人ラインを、全体LINEに誤爆していた。
もういろいろと問題だったが、とりあえずは、どうにかまこが起きる前に送信取り消しをしてもらわなければ。必死で個人LINEを送った。「間違いですよね?お願いです、取り消してください。」
だが、言いたいことを言ってスッキリしたのかよく眠っているようで、昼過ぎまで削除されることはなかった。LINEをみたまこは全体LINEを退出した。これで、わたしたちの”ファミリー”は崩れ落ちた。メンバーとコミュニケーションを取れなくなったXは半年後に解任された。
そして、俺が必ず売るんでお願いします!と言ってヨーロッパツアーまでご一緒してくれたマネージャーも、他にやりたいことを見つけたらしく、color-codeを後任に託してあっさり転職していた。
これで、color-codeの元に残ったのは、おっちょこちょいマネージャーの後任で入った新卒3年目の女性マネージャー、メンバーと一緒に現場を回り、Xからコテンパンにやられていた、サトちゃんだけだった。自分一人でcolor-codeを売っていけるのか不安がっていたサトちゃんを、color-codeは三人がかりで説得した。「これからは、四人三脚で頑張ろう、そしたら、絶対上手くいくから!!!」わたしたちはやっと、燃えはじめていた。
ここから、サトちゃんとcolor-codeの、四人体制の行進が始まった。2018年が終わろうとしていた。
(つづく)
◆MARISAコラム「この世界の片隅で -color-codeの奇跡-」まとめページ
◆color-codeオフィシャルサイト







