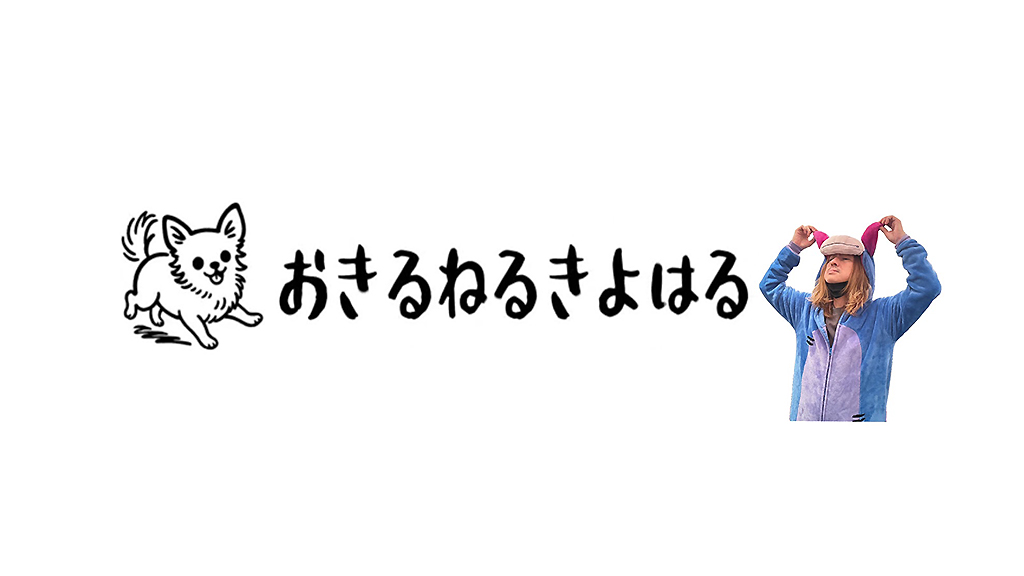【インタビュー】清春、新たな選択肢としての配信 “今こそ考えたい、選ばれる理由の大切さ”

■ファンに支えられながら活動している状況下に
■それ以外の層にアピールしようとする矛盾
──そうした状況下、演者の側も鑑賞する側もライヴに飢えているとなれば、少しでも実際のライヴに近いものを届けたいと考えるのも当然だと思うんです。だからこそ配信だけども特効とかを存分に仕込んでみたり、あたかも目の前に大観衆がいるかのように大声を張り上げてMCをしたり。
清春:うん。そういう日がたまにはあってもいいのかもしれない。それが、たとえばファンクラブ会員じゃないと配信チケットが買えないとかね、そういうことでいいと思うんです。ただ、そこまでのファンじゃないような人がお金を払って観てくれてる可能性もあるわけじゃないですか。毎回は観ないにいても、何かを見て思い出してくれる人とかね。だけど僕にとってそういう人たちというのは“久しぶりに会えた、その場限りのお客さん”という感じなので、そこに向けてやる必要はないなと思っていて。
──いわゆるグレーゾーンからの反応は気にしない、ということですか?
清春:うん。そういう人が知ってる僕というのはたいがい、かなり昔の僕で。そういう人たちに限って“変わっちゃったね”とか言うわけですからね。前にカヴァーアルバムを出した時とかも久しぶりに聴いてくれた人が結構いたみたいで、そういう反応とかがSNS上にも多かったらしいんだけど。それこそ激しいアプローチをしてた頃の僕しか知らない人たちは、今が意外なんだろうし、実は昔よりも歌のキーが上がってたりすることなんかもわからないし興味もない。今って、歌本来の圧とか、抑揚とか、要するに“どう歌うか?”っていう部分が結構スルーされがちな世の中になってる。ホントはそこがいちばん大事なんだけどなあ、ヴォーカリストにとって。YouTubeから出てきたとか、TikTokで有名ですとか、そんなのばっかりじゃないですか。あれはもはや、僕らがやってる音楽とは違うもの。僕らは長年、ファンの人たちによって生かされていて、そこでやろうとしてるのは、もっとすごい歌を歌えるようになる、前回よりもいい歌を歌えるようになるってことであるはずなんです。お金を払ってもらう価値はそこにあると思ってますから、それが配信であっても。
──YouTubeから生まれたヒット曲を否定するつもりは毛頭ないし、いい曲はいい曲、上手い人は上手いと思うんですけど、なんか“ミュージシャンっぽいことやってみた”でしかないケースもあると思うんです。ところが最近はミュージシャンの側が“YouTuberっぽいことやってみた”な感じになってきている。
清春:そこは切ないですね。たとえば生配信して投げ銭をしてもらえる、ツールとしては手軽で面白いですよね。地方のライヴハウスをドサ回りするよりもずっと効率はいいだろうし、観てる人はそれでもいいだろうと思うんですよ。ただ、なんかコロナが直接関係してるのかどうかわからないし、そうなってから余計そうなってるのかもしれないけど、ホントにここ5年とか10年って、アーティストのプレイの質の高さが、ないがしろにされつつある。やる側にも、音楽はお金を作るための手段でしかないというか、椅子取りゲームみたいになってる。カードをたくさん集めたほうが勝ち、こういうことをやってこれだけ視聴者がいると月々いくら入ってきますよ、みたいなところしか見ない。もちろん新しい価値観を否定するつもりはないし、新しい価値観の中にも古い価値観の中にも良いものと悪いものがあると思うんだけど、それにしても今は新しいことに合わせるのが正しい、みたいなことになっちゃってる気はする。
──今の時代、ミュージシャンとして活動するならこういう手法が効率的に実益に繋がりますよ、みたいな部分にばかり目が行き、音楽そのものが二の次になっている、と?
清春:そういうことです。ただ、もちろんそれで生活できるようにすることも大事だろうけど、そこである程度生活できるようになったなら、その後はもっと音楽を突き詰めるべきだと僕は思います。それまでは勝ち負けのゲームでもいいんですけど。おそらく今って、お金持ちになることが絶対的に正解なんです。だからミュージシャンが職業意識からYouTubeをやるというのもべつに悪いことではないと思う。だけど僕ならそこで、“ファンの人たちの力を借りながら成立してるのに、なんでファンの人たち以外に向けてアピールしようとするのかな?”と思うわけです。
■『ロード・オブ・カオス』の暗黒世界にみる
■ロックが本来持ち合わせていた危険さ
──そこで拡がりを求めようとするのは、まだ自分としてのテリトリーを確立できていないという不安の現われでもあるのかもしれません。ただ、簡単に広がりを求められることには当然のように危険さも伴ってくるというか。
清春:そうですよ。たとえば僕の場合、たまにテレビに出る場合でも、あくまで清春として出てるわけです。べつにそこで新しいファンをゲットしようという気持ちもなければ、トレンド入りしたいわけでもない。そういう場で、素人がバズるみたいな感覚の真似事に手を出しちゃうのはキツいかなあ、と思う。今、まともに音楽を突き詰めようって人があまりにも少なくなっちゃってますからね。ところで、観ましたよ、あの映画。『ロード・オブ・カオス』でしたっけ?
──はい。試写にご案内したんですけど、率直なところどうでしたか?
清春:この映画の概要はなんとなく把握したうえで観たんですけど、すごく個人的な感覚で言うと、主演の2人の配役が逆だったら僕としてはもっと共感できる部分があったかも。
──ユーロニモス役のロリー・カルキンとヴァーグ役のエモリー・コーエンが逆だったら、ということですね?
清春:そう。あくまで映画の中での話ですけど、ヴァーグはユーロニモスとかデッドほどイケてない感じがするじゃないですか。ところが話が進むにつれてどんどんヴァーグの存在が大きくなってくる。そこでちょっとイラっとしました(笑)。
──興味深いです。実は僕も、実際のルックスと照らし合わせながら同じようなことを感じていたので。あくまでヴァーヴではなくユーロニモスを主人公する物語として描かれたからこそこうなった、という部分もあるんじゃないかとは思います。
清春:なるほど。でもこれ、実話なんですよね? すごいなあ。
──いくぶん脚色も入っているはずですし、真実とされていることが誰かの嘘だったりする部分もあるとは思うんですけどね。ただ、美学が誤った方向に暴走したり、小さな世界の中で競争意識がエスカレートし過ぎたりすると取り返しのつかない事態になる、というのはブラックメタルの世界に限った話ではないと思うんです。実を言うと僕自身、この原作に当たる本を読んだ時に、初期の黒夢の世界に通じるものを感じたところがあって。
清春:なるほど(笑)。ただ、もちろん教会を燃やしたりするわけじゃないにしても、“コレをやると伝説になれる”みたいなことがあれば、その事件性で話題をさらうというのは、確かに昔の僕らがいたシーンでは少なからずあったことで。ただ、それが度を越してしまうともはやエンターテインメントではなくて、本当に怨念の世界じゃないですか。実際、ユーロニモスの戦略、レーベルとしての戦法とかについては頷けるところがあったし、僕は事実をよく知らないから“なんでカッコいいわけでもないヴァーグがこんなに幅を利かせるようになるわけ?”と思っちゃった(笑)。でもまあ、本気の人が現れるとヤバいことになり兼ねないですよね。
──ええ。“POSER”という言葉の使われ方も印象的でしたよね。言葉自体は本気じゃない人間を蔑むものですけど、だったら僕はPOSERでいいや、と思わされてしまいます。
清春:いや、僕も(笑)。ただ、もちろん人を殺しちゃ駄目だけど、ロックというのが怖いものだったというのを思い出させるという意味では、いい映画だと思いますね。きっとこの人たちはみんな、本気だったんだろうと思うし。ユーロニモスが『ケラング!』誌に載って、全部自分のことみたいに喋ってる、という話もリアルでしたね。昔、自分の身近なところにもそういう話は確かにありましたもん。しかしすごい映画が作られたもんですよね。ああいう現実が過去にあったってことを踏まえると、確かに現代は生ぬるいってことになる。ロックは危険な匂いのするものであるべき、みたいな感覚って今の子たちにはわかるのかな? なんか僕は、普通にこの映画のグッズとか欲しくなっちゃったけど(笑)。