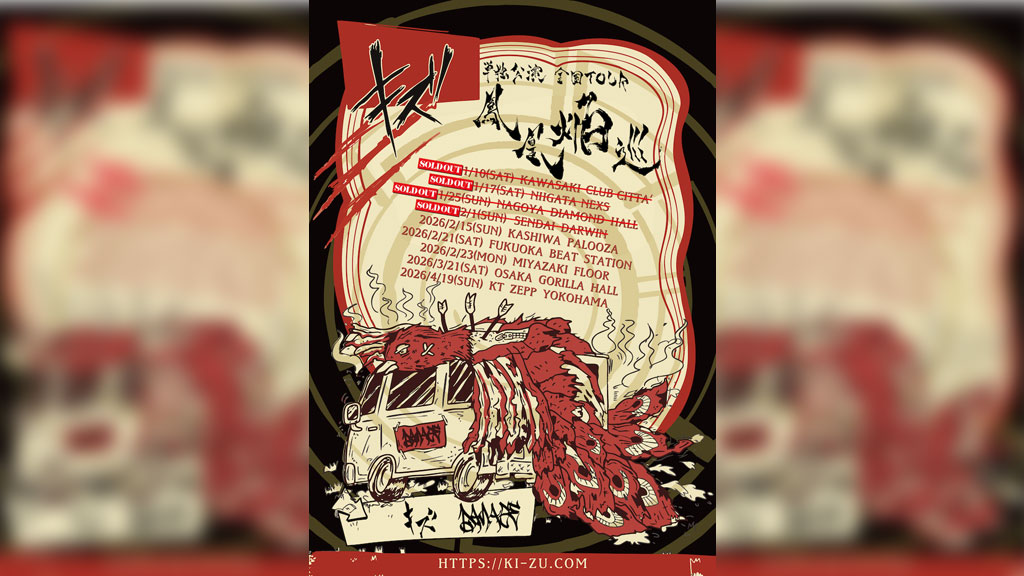【インタビュー】キズ・来夢、「ライヴをすることで生きていくことを赦される」

■「自分が理想としてたのは、音楽に乗せてこんなことを歌うことだったのか?」と思わされた
──いずれにせよ来夢さんが求めているのは、何かについて考える切っ掛けになることなんですね? たとえばRAGE AGAINST THE MACHINEは政治的な主張も強いバンドですけど、かつて彼らのTシャツがファッションアイテムのように持て囃されてしまい、それを買うためにライヴに来る人たちが行列をなすような事態になったことがありました。ただ、当時の取材でそうした現象についてどう思うか尋ねたところ「いつかそのTシャツにプリントされた絵柄や言葉の意味を理解したり、そこで何かを考える切っ掛けになったりする可能性があるならばそれでいい」との回答が返ってきたんです。来夢さんが考えているのもそういうことなのかな、と。
来夢:そういう意味では、そこは同じかもしれない。何かの切っ掛けになること、興味を持ってもらうことが僕の求めているすべてなので。
──先ほどの発言の中に「日本のロックバンドとして」という言葉も出てきました。日本に生まれ育った自分、というところで意識も結構強いんでしょうか?
来夢:そこは僕、やっぱ特殊なんですよね。中学生の頃に留学を体験していたりとか。その当時に限らず海外とかに行く機会があるたびにアジア人差別だったり日本人差別というのを体験してきて。たとえば、向こうでも当然、中学で歴史を習うわけですよ。でも、こっちの歴史と向こうの歴史とでは教わる内容がまったく違うわけです。
──ええ。外国で世界地図を初めて見た時には驚きますよね。日本が真ん中に描かれてはいませんから。
来夢:そうなんですよね。向こうでの歴史の授業では、日本人にとって良いイメージではないこともたくさん教わることになる。逆に言うと、日本で教わる歴史の中では美化されているような部分があるわけですけど。ただ、もちろん教科書とかに露骨に酷い表現で書かれているわけではないにしても、歴史上、実際この国だって良くないこともしてきたわけじゃないですか。で、そういう内容の授業があると、やっぱ虐められることになるんです。単純に、日本人だからという理由で。もちろん抵抗はしてきましたし、そういう日常を生き抜いてきたという自負もあるので、そのぶん人一倍、日本人としての誇りを持てるようになったのかもしれない。海外については結構何度も行ったり帰ってきたりを繰り返していて。僕自身、行きたくて行ったわけじゃなく、少年期にちょっといたずらをし過ぎて両親から「お前はもう向こうにでも行け!」と言われてそうなった感じなんですけどね(笑)。
──つまり、英語で生活していた時期が結構あったわけですね?
来夢:はい。当初はもう「絶対日本語だけで押し通してやる!」ぐらいの勢いだったんですけど、それだと食いたいものも食えないし。たとえばチップスを注文して、ポテトチップスが出てくるもんだと思ってたらフライドポテトが出てきて、「そうか、フィッシュ&チップスのチップスはそれか!」みたいに気付かされたり(笑)。そういうところで閉じてるのってやっぱ嫌じゃないですか。あと、音楽についても同じようなところがあって、最近はどうなのかわからないけど、当時は向こうにカラオケってなかったんですよ。
──カラオケがあるのは一部のバーやパブだけで、未成年が普通に利用できるカラオケボックスみたいなものはないですよね。
来夢:そうそう。だからみんなで集まって歌を歌うとなると、演奏しないとならなくなるんですよ。それでガレージとか倉庫で楽器を鳴らすようになったりとか。そこで身についたものというのが結構あったと思いますね。向こうに行くようになる前からバンドはやってたんですけど、そんな日常の中でいっそうバンド志向になっていって。練習場所はお菓子の倉庫でした。会議室ぐらいの部屋の半分ほどはお菓子が山積みになっていて、そこにドラムとかアンプとか持ち込んで、みんなで昼間からやってましたね、学校さぼって(笑)。それで結果、自分としてはパワーアップして帰ってきました。
──もう自信満々な感じで?
来夢:いや、そんなことはなかったかな。当時はそこまで自信もなかったし、自分を強くしてくれたのはやっぱ音楽だと思うんです。今、こういうことを自信をもって歌えるようになったのも、このキズっていうバンドを組んで、この年齢になってからのことというか。ようやくこうなれたんだって考えると、まだ当時はだいぶ弱かったですよね。そんな自分の気持ちを歌にして反抗しようっていう力が身につくまでには、やっぱ結構時間がかかりました。
──少年期の経験、それ以降のバンド経験をはじめとする流れ。そうして時間を経てきたことで、さまざまなことが実を結ぶようになったということなのかもしれません。
来夢:実を結んでいる……そういうことなのかもしれないですね。正直、自分ではあんまり過去のことを振り返ったりもしないし、よくわかんないんですよ。いつ、どのタイミングで自分がこういう思想になったのかとか。でも絶対、そういう転機みたいなものがあったはずだとは思う。
──それこそ何かに切っ掛けを与えられるような機会があったのかもしれませんね。
来夢:そうですね。で、今回の「リトルガールは病んでいる。」という曲について言うと、切っ掛けになったのはウクライナのニュースというか、プーチン(ロシア大統領)の演説だったんです。僕、ニュースを見るのがわりと好きなんですね。そこでウクライナに関するニュースも日常的に見ていて、ある時のプーチンの発言に、核の使用についての日本人の意識に訴えかけようとする言葉があったんですね。「報復の権利」みたいな。そこで僕の中で、何かが湧いちゃったんです。日本人はそういう痛みを必死に耐えて、乗り越えて、平和をつかんできたという歴史があるわけじゃないですか。その平和をそんなふうにして、また無に戻そうとするかのような発言がホントに許せなくて。
──そうした気持ちを抱いた時にこの歌詞を書かずにはいられなかった、と?
来夢:そういうことです。ただ、この曲がアップされた時のYouTubeのコメント欄とかを見ていたら結構勘違いされてるケースが多くて。べつに僕は反戦歌を書いたわけじゃないんですよ。ただ、そういう現実に興味を持ってもらいたいだけなんです。僕としては日本の歴史もわかってるし、向こうからすればそれが普通どういう見え方になるのかも知ってるつもりなんですね。ただ、実はこの曲を書いてる途中でホントに虚しくなっちゃったことがあって。僕は、自分が憧れてきたヴィジュアル系という音楽をやっているわけですけど、本来はもうちょっと夢とかそういうものがあるものだったと思うんです。そこで「自分が理想としてたのは、音楽に乗せてこんなことを歌うことだったのか?」と思わされて。
──ああ、それはちょっと辛いかもしれませんね。
来夢:そんな現実に突き動かされて歌おうとしてる自分のことが、なんかすごくせつなくなっちゃって。そういうところでの葛藤も、実は結構あったんです。ただ、結果的に僕が伝えたかったことというかホントに言いたかったのは、その詞の中の一文に過ぎないんです。「そろそろ僕も入れてくれ、宇宙の暇人に」という部分。“宇宙の暇人”というのはhideさんの「ROCKET DIVE」にも出てくる言葉なんですけど、あの曲ではロケットが飛んでるのに対して、僕の時代はミサイルなんですよ。なんかそんな現実にも虚しくなっちゃって、「なんだろう? これでいいのかな?」っていうような気持ちになってしまって。
──かつて自分が力をもらってきた音楽には夢や希望、背中を押してくれるような力があった。それに対して今の自分は不安定な感情を吐き出してるだけではないか、みたいなところでのジレンマというか。
来夢:そうです、そういうことです。
──なにしろ今は、純真無垢なリトルガールですら病んでしまうような世の中になっているわけですよね。
来夢:そうなんですよね。まあ、その「リトルガール」という言葉自体は広島のリトルボーイ(アメリカ軍により広島に投下された原子爆弾のコードネーム)に呼応するものでもあるんですけど……「僕が夢見てた音楽ってこういうのだったっけ?」という葛藤があったわけです。だからこそ「僕もそろそろ入れてくれ、宇宙の暇人に」と言いたかったんです。
──きっと桃色の雲の上の人からは「まだまだ早いぞ」と言い返されるでしょうが。
来夢:でしょうね。でも、それこそ歌詞にもあるように「自転車で月まで漕いで」行ったら入れてくれるでしょ、という気持ちもそこにはあって。
──僕自身もこの曲を初めて聴いた時に“宇宙の暇人”というワードに反応しましたが、今ようやく謎が解けたように思います。以前の記事の中で来夢さんは「常に、その時に思っていることを歌いたい」と発言していたことがあります。つまり、これまで歌ってきたものもすべてその時制で書かれたものだということですよね? 実際、人の気持ちというのは変わっていくものだし、それが常に反映されているのであれば、歌詞に一貫性がなくても当然だと思うんです。そこで辻褄合わせみたいなことをしてもしょうがないというか。
来夢:はい。だからそういうことはしてないですね。なんかもう、自分でいること自体がコンセプトみたいな。僕が何を思ったか、これから何を思うのかがキズのコンセプトということでもいいのかな、と。そこはもう受け入れて、とにかく自分が思ったことを素直に書いて。仮にそれが酷い言葉だったとしても、それが真実だったりすると思うんですよ。だからまあホントの気持ちを隠すことなく、今はもう腹を括ってやってます。べつに売れようとか「みんな、こういうの好きでしょ?」とか、そんなのを基準にして言葉を選ぶことはなくなりましたね。自分がホントに言いたいこと、思ったことをブログみたいに書いてます。

──たとえば今回の「リトルガールは病んでいる。」が今後どうなっていくかはある程度時間が経たないとわかりませんが、過去に書いてきた歌詞の中には、若気の至りで書いたものとか、今となっては気恥ずかしさが伴うもの、「今だったらこんなこと書かないのにな」といった後悔めいたものが伴うものもあるだろうと思うんです。それを歌い続けていくことって、苦痛になりませんか?
来夢:ふふっ。だから僕、歌詞変えるんです。
──ずるい!(笑)
来夢:ははは! たとえば「おしまい」っていう1stシングルにはちょっと語ってる部分があるんですけど、それがどうしても意味わかんないというか間違ってると今は思えるんで、だいぶ早めにそのフレーズはライヴでは歌わなくなっていて。今の自分としては絶対間違ってるなと思える言葉とかについては、歌わないようにしてますね。
──つまり音源上での歌詞というのはその時点での記録に過ぎなくて、最終形であるとは限らないということなんですね?
来夢:そうです。音源ではなくあくまでライヴで完成に至るものだと思っているんで。音源上の歌詞は、そのためのガイドでしかないです。だから変な話、クオリティ高く音楽を作ろうとかそういう意識もない。クオリティの高いライヴができればそれでいいんです、僕は。
──来夢さんは“音”というよりも“言葉”の人であるはずですよね?
来夢:それは間違いないです。音はむしろ嫌いですね。作曲がホントに嫌いなんですよ。何よりも僕は機材とかが大嫌いで、そういうものに囲まれた部屋とかはマジで耐えられないですね。スピーカーがドーンと置かれてる、みたいな。
──逆にそういう環境でこそ落ち着く、という人もいるはずです。
来夢:みんな大好きなんじゃないですか? でも僕にはあの感覚が理解できなくて。多分そもそも音楽があんまり好きじゃないんですよね。オーディエンスの前で何かするのは好きなんですよ。だけど一人で居て、誰も聴いてくれてないところで音楽を作るっていうのはちょっと……。だから僕の場合、MacBOOK一台で、オーディオインターフェイスに繋がずに、イヤフォンとかで聴きながら曲を作っていて。自分の声を録音する時もMacの内臓のマイクで録っちゃうくらいなんです。
──ことにこのコロナ禍にはそういった録音環境の整備に力を入れてきたミュージシャンも多いようですけど、そうした傾向とは真逆なんですね。
来夢:みんなすごいですよね。僕の場合、仮に「自宅スタジオ見せてください」みたいな専門誌の取材とかがあったとしても、見せるものがまったく何もないんで(笑)。まあ、海外で作ったりすることもあるんで、コンパクトな形でやれるのがいちばん都合いいというのもあるし、いつも持ち歩いてるのはそのMacBOOK一台だけなんです。出先ではホントに助かるんですよね。