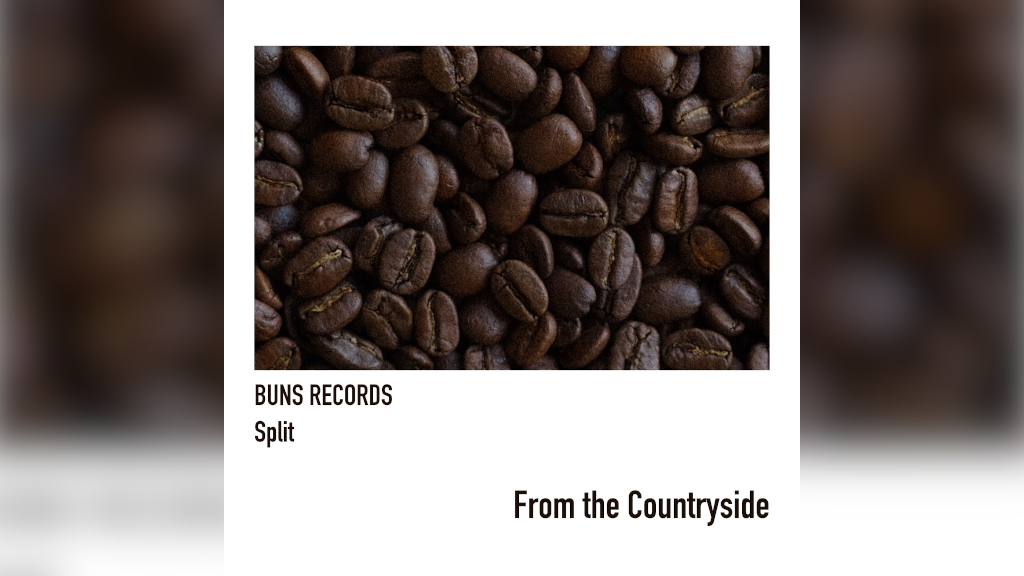【インタビュー】Atomic Skipper、メジャー1stフルアルバム『Orbital』発売「これを聴いてもらえたらAtomic Skipperがわかる」

■メンバー4人の結びつきをお客さんへ届けなきゃという使命感
── いろんな楽曲がありますけど、久米さんが何か1曲挙げるとすれば?
久米:僕は「周回軌道列車」ですね。今まではAtomic Skipperの武器なのに鳴りを潜めてた部分というか、“衝動的なところ”が出てると感じてて、しかもいろんなライヴやレコーディングを経験して上書きできた感覚もありました。今回の制作はかなり1曲1曲に向き合い続けていたので体がこわばるような感覚もあったんですが、「周回軌道列車」のときは楽しみながら新しいことに挑戦できてる感じがしたんですよね。
── この曲はいろんな解釈ができる歌詞だなと思ったんですけど、中野さんはどういう気持ちで歌おうと考えましたか?
中野:聴いてくれる人のことを、もっとひとりの人間として捉えたいなと考えました。そんなつもりはなかったんですけど、それまではリスナーさんのことをどこかひと括りにしてる部分もあったんじゃないかと思って。
── あ〜、全体へ向けて歌っていたような。
中野:例えば、「この間は東京にいたのに、今日は大阪にいる!」みたいなお客さんに対して、「そういう人ってどんな人生を歩んで、どういう気持ちで私たちを観に来てくれてるのかな?」とか、よりその人をひとりの人間として深堀りしたいというか。歌詞に<話し足りないや>ってあるんですけど、もっと知りたい、もっと教えて欲しいっていう気持ちがリアルに吹き込まれてると思います。
神門:こういうふうに、曲の解釈が僕とヴォーカルで違うのはAtomic Skipperの面白いところだなと思っていて。僕は他者を鮮明にイメージするのがあんまり得意ではないというか、先ほどもお話させてもらったように楽曲にする感情がめちゃめちゃ内側へ向いてたりするんですよね。だから、リンクしてる部分はあるけど、(中野は)より外側へ向けてる。いろんな捉え方ができるという印象は、そこを狙って作ったというより、メンバー4人がそれぞれの咆哮を見てるからこそ生まれたエッセンスなのかなって、ちょっと思います。
── では、松本さんが1曲挙げるとしたらどの楽曲になります?
松本:「生き抜く人」っていう、結構いちばん最後くらいに完成した曲なんですけど、神門さんのイメージとこちらのイメージがなかなか合致しなかったんです。途中まではこちらから提案もしつつっていうスムーズな流れだったんですけど、最終的にこの楽曲はかなり苦労しましたね。
── そういった場合、神門さんは自分の方向性へ引っ張るようなことはしないんですか?
神門:もっと寄り添って欲しいという気持ちが強かったとしても、プレイヤーとしての視点はわからないじゃないですか。言ったら、僕が彼らよりもベースやドラムが上手だったりはしないので。あと、これは自分も弱かったところなんですけど、他の楽曲に比べるとこの曲はイメージしてたモノが薄かったんです。どう転ぶのか自分でもわからないというか、そこが歌詞にも凄く出てたり。ただ、そうなったとき、ひとつの指標になるのは歌詞や歌に対してのアプローチ。楽曲の完成度を上げるのは最終的にはそこだと思っていて。結果、楽器隊3人で諦めずに試行錯誤したら凄く良くなりました。
── そういうシビアな制作現場を、中野さんは確認しに行ったりもします?
中野:私は遠くから見てます(笑)。バチバチってなったとき、行ったほうがいいかなと相談したこともあったんですけど、やっぱり3人で話したほうがいいということになりました。
── でも、そういうスタンスだとお互いにいいプレッシャーになるというか。責任を持って仕上げるぞ、っていう。
中野:そうですね。楽器隊3人が構成やアレンジで頭を悩ませてるとき、私はどれだけ歌に向き合えるかをずっと考えていました。もっと細かい部分、言葉の裏側まで表現できるように、って。激しくやり合ってるっていうのを耳に挟みながらも、自分はやるべきことをやるっていう、いいバランスになってるかなと思います。
── そういった中で、思い入れがある楽曲をピックアップするとしたら?
中野:再録した「ロックバンドなら」ですね。やっぱり、以前もひとつの形になってるので、「聴き比べたときにどうだろう?」って考えちゃって。そうなると、余計なことも浮かんできたりしたし、レコーディングへ向けて自分は本当はどうしたいのかを突き詰めるキッカケになったんです。
── そこで気づいたことは何だったんですか?
中野:小手先のテクニックじゃなく、ライヴに来てくれる人のことをひとりひとり鮮明に思い浮かべて、ここにどれだけの人が関わってくれているのかをより考えることが歌ににじみ出るだろうな、って。いろんな意味で思い入れが深いのは、この曲です。

── 代表曲でもありますし、Atomic Skipperのバンド観が詰め込まれた楽曲だと思いますが、制作した時点から数年が経っています。この楽曲に対する捉え方が変わったところもありますか?
神門:作ったのはコロナ禍に入るちょっと前で、当時はかなり内向きというか、自分たちの想いが凄く強かったんです。その後、ライヴを重ねる毎にテンポも完成度もパワーも上がっていき、お客さんにも「やっぱり、Atomic Skipperはこうだよな!」と感じてもらえる存在になったというか。最初はメンバー4人で「ロックバンドなら」を掲げていたけど、今は「ロックバンドなら」という楽曲がAtomic Skipperのライヴにおいて共通言語化しているのが凄く嬉しいなと思っていて。だから、再録するときもライヴでやってきたことを忠実にやろうとして、わりとこう、全員が一発勝負なところもあったんです。
中野:歌は1テイクをベースにしてますね。
神門:ベースとドラムも一緒に録りました。あと、「間に合ってます」もそうだったかな。
── 「間に合ってます」は2ビートで駆け抜けるショートチューンですしね。
神門:もちろん、ライヴに来てくれる人だけが僕たちを支えてくれるとは思ってないし、ずっと聴いてくれてる人たちも同じなんですけど、やっぱりライヴに来て欲しいという気持ちがあって。楽曲によってレコーディングの仕方を変えたんですよね。
久米:たしかに以前と今じゃ感じ方が全然違うなって思いますね。コロナ禍にリリースしたのもあって、いちばん世の中が大変な状態のとき、僕らが歩みを止めない為の楽曲でもあったんで。
中野:そうだったね。
久米:メンバー4人の結びつきがいちばん大事で、ひとつになってお客さんへそれを届けなきゃっていう、使命感みたいなことを考えた時期でもあって。だから、ライヴでも1曲目にやることが多かったんです。今はそこから自信を持ってというか、両手を広げてやれる楽曲になったのかなと思ってますね。
── ライヴでプレイするたびに初心を思い出すでしょうし、背筋も伸びますよね。
中野:そうですね。私も人間だから心の波があるけど、この楽曲が変わらず側にいてくれて、同じようにお客さんも大事な曲だと感じてくれているのがホントに心強くて。落ち込んだり、悩んだりしてもこの楽曲があればきっと救い出してくれると思ってます。