魂の扇動者

| 魂の扇動者 |
| このことはストレートに受けとめよう。 Sinead O'Connorは2児を抱える未婚の母で、マリファナを吸い、ラスタファリアニズムの言葉を話し、異教信仰への関心を自由に語り、全米生放送のテレビ番組でローマ法皇の写真を引き裂いたこともあるにもかかわらず、保守主義で知られるキリスト教の宗派Latin Tridentine Churchから聖職者の地位に任ぜられている。 確かに人類は本質的に矛盾する動物だが、この一件は“幅広く活動する”ということの概念を新たなレベルへと導くものと言えるだろう。 本当にそうだろうか? '80年代中盤にとてつもなく才能豊かなティーンエイジャーとしてポップシーンに初登場して以来、彼女の音楽には強力な精神性が注入されてきた。 聞き間違いようもない彼女の歌声に常に存在する痛みは、神と一体になりたいという一貫した希求を訴えており、それはどのような単一の教義でも満たすことができないくらい大きな飢餓感である。ある意味で長年にわたるの彼女の行動と発言のすべては、彼女が生来の飽くなき探求者であると考えれば納得できるだろう。 「私のファーストアルバムは『The Lion And The Cobra』というタイトルだった」 彼女は説明する。 「あれは神を信じる者はライオンやコブラを踏み付けにすることができるという詩篇第91番から取ったものなの。つまり、彼らは大いなる困難や障害を乗り越えて自己あるいは魂に到達できるという意味よ。それはキャリアをスタートしたときからの私の信念で、極めて精神的な道のりをずっと歩いてきたと思っているわ」 それでもなお昨年TridentineがO'Connorの聖職授任を許可したことが完全に説明されるわけではない。高僧たちが明らかに不敬な発言をしている彼女のような存在を組織内に認めるとは思えないのだ。 だが、実際のところはわからない。教会がイメージを変えたいと考えたのかもしれない。いずれにせよ、この件はO'Connorあるいは聖職名Mother Bernadette Maryがマスコミと話したいような問題ではない。 「いくつかの理由があって聖職の件については話したくないの。PRのためにやったわけじゃないわ。私のレコードと関連づけて話したりしたら、パブリシティに利用したと思われてしまうでしょ。そんなことしたくないの。それと極めて重要な点は、私は教会に不敬を働くつもりはないし、すべてのカトリック教徒や女性が聖職に就くのを問題視する人々に二本指を突き立てていると思われたくないのよ。教会は私に対して大いなる寛大さを示してくれたし、私が不敬な行為に及ばないかぎり、向こうも私を尊重してくれるでしょう」 Tridentine教会がパブリシティのためにO'Connorを授任したかどうかの疑問はしばらく置くことにして、『Faith And Courage(信仰と勇気)』というぴったりのタイトルがつけられた6年ぶりのフルアルバムとなる彼女の新作に話を移すことにしよう。 この作品は幅広いプロデューサーやミュージシャン(有名どころではWyclef Jean、 Brian Eno、EurythmicsのDave Stewartなど)とのコラボレーションの産物だが、内容的には一貫したテーマにフォーカスがあてられたものとなっている。 そのテーマが精神の問題に正面から取り組んだものだと知ってもおそらく誰も驚くことはないだろう。ヒット性の高い第1弾シングル「No Man's woman」で、Sineadは男性に頼って自己確認することにうんざりして、代わりに神に頼るようになったと歌っている。 だが、これはひとつの解釈に過ぎないわけで、彼女自身の考え方は少し違っているようだ。 「「No Man's woman」は慎重に耳を傾けるべき曲で、特に詩の内容には注意して読む必要があるの」と彼女は警告する。 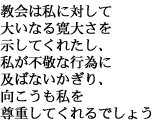 「この女性は男性の魂と深い恋に落ち、男性から大きくインスパイアされたり敬意を受けていることについて話している。彼女が師と仰ぐのはすべて男性で、男性とはもっと精神的なつながりを深めたいと望んでいるけど、性的な関係や妻やガールフレンドになることは求めていない。だけど、彼女は男性から得た他の素晴らしい数々のことについて、どれだけいとおしく思っているかを語り続けるの…。アルバムではこうした魂という概念について、つまり我々の外側を飾るものを求めるのではなく、内面を探求していくということを取り上げている。だから、実際にあの歌では男性というものは、我々が求めて止まない人間の外面にあるものを象徴する存在として使われているのよ」 「この女性は男性の魂と深い恋に落ち、男性から大きくインスパイアされたり敬意を受けていることについて話している。彼女が師と仰ぐのはすべて男性で、男性とはもっと精神的なつながりを深めたいと望んでいるけど、性的な関係や妻やガールフレンドになることは求めていない。だけど、彼女は男性から得た他の素晴らしい数々のことについて、どれだけいとおしく思っているかを語り続けるの…。アルバムではこうした魂という概念について、つまり我々の外側を飾るものを求めるのではなく、内面を探求していくということを取り上げている。だから、実際にあの歌では男性というものは、我々が求めて止まない人間の外面にあるものを象徴する存在として使われているのよ」このようなテーマはヘヴィに感じられるかもしれないが、楽しくポップなメロディーや弾むようなヒップホップのビートに乗せられれば、非常に受け入れやすいものとなる。 実際のところリスナーの受け入れやすさという点は、『Faith And Courage』における主要な特徴となっており、物鬱げなバラードと小気味よいロックが基調となっている。 かつてのドラマティックで怒りに満ちたSinead(例えば『The Lion And The Cobra』の「Troy」や'90年の『I Do Not Want What I Haven't Got』の「The Last Day Of OurAcquaintance」)も時には聴くことができるが、激しい怒りは赦しの精神によって緩和されている。 アルバムで最も強烈なトラック「Daddy I'm Fine」は当初こそ父権性への果敢な挑戦と思えるが、最後は優しく誠実な“I Love You”で結ばれている。 「今では私も33歳」 O'Connorはつぶやく。 「確かに対決的な姿勢は少し薄れたわ。自分の言っていることに自身が持てるようになったからよ。若いころには自分が何について語っているか確信がないから、誰でも防御的になってしまうものなの。歳をとるにしたがって、人を脅かさないような方法でコミュニケートする手段を覚えていくのよ。だけど対決姿勢は非常に有効なこともある。大事なのは議論から逃げ出さないということね。時として相手との議論をいとわないほど誰かを愛するということはとっても大切なことよ。世界には非合理なくらい怒りへの恐れが満ちているわ。怒りというのはもっと尊重されてしかるべき感情だし、健全な方法で怒りを表現する場所が与えられるべきね…。それはずっと音楽の役割だったはずよ。つまり、ある種の人々がある種の非常に困難な感情を表現するための安全な場所という意味でね」 Sinead O'Connorにとって'90年代はタフな時代だったことは疑う余地もない。 彼女の音楽は次第に惨めな特集記事の中における単なる小見出しのような存在になってしまっていた。彼女はメディアと大衆の両方から誤解されて攻撃を受け、娘を保護するために戦わねばならず、精神的なトラブルのために一度ならず自殺を試みる羽目になった。 復活した彼女の姿を見てその声を聞くのは心強いものの、彼女がいまだにどこか混乱しているように思えることは否定しがたいところでもある。 自分は現在レズビアンだと考えているという先頃の(このインタヴューが行なわれた後での発言)彼女の主張は、『Faith And Courage』のリリース直後だっただけに、本来の意図は(何かあるとしても)不明確なままだが、どこか計算の匂いがする(これによって「No Man's Woman」も解釈のされ方が変わるのは確かだろう)。 また、数カ月前に起きた元PoguesのShane McGowanのドラッグ逮捕劇において密告をした友人というのがSineadだったと明らかにされたことは、頭痛のタネともなっている。彼女の行動は善意に基づくものだったのかもしれないが、共感するのは難しい。自分の仲間に対して警官をけしかけるというのは、全くもって厳しい愛情である。 それでもなお、Sineadがひとたび口を開いて歌いだせば、あれやこれやの文句はすべて吹き飛んでしまう。 '90年代のほとんどの期間、我々は心を貫くような彼女の歌声の劣悪なイミテーションに堪え続けてきたと言えるだろう。 『Faith And Courage』を聞けば、例えばAlanis Morissetteのような人ですらO'Connorのヴォーカルスタイルに大きく影響を受けていることが、すぐにわかるだろう。それだけに本物の歌声を再び聴けることは、よりいっそう大きな喜びである。 O'Connorは語る。 「“どうやってあんなにパーソナルな歌が作れるの?”なんて質問を受けるたびに驚いてしまうの。だってそれは“あなたの顔に鼻が付いているのを知っていますか?”と訊かれるようなものだから。すべての歌は個人的なものよ。“a-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom”でさえ、極めて親密な個人的発言でしょう? 難しいことじゃないわ。みんなが自然にやっていることなの」 by Mac Randall |