【対談インタビュー】事務所代表とA&Rが語る、「H△G」のビジョン

日本語でしか表現できない“懐かしい”や“切ない”といった概念を可視化し、世界中に発信する次世代 J-POP アーティスト・H△G。
ボーカルChihoを中心としたコンポーザー&クリエイター集団として2012年より活動している。2019年よりさらに幅広いタイアップソングに恵まれ、2020年3月にリリースしたBlu-rayアルバム『瞬きもせずに』の表題曲がテレビドラマ『ゆるキャン△』オープニングテーマに起用されたことからCD化を望む声が増え、その期待に応えるかたちで2021年2月に新曲3曲を加えたCDアルバム『瞬きもせずに+』をリリースする。
数多くのタイアップに恵まれ、H△Gの市場は広がりを見せているが、覆面アーティストゆえにまだまだ謎も多い。今回BARKSではそれを解明すべく所属事務所・プラスデザイン株式会社代表の丹羽文基氏と、所属レコード会社・ドリーミュージックA&Rの峯松亮氏との対談を実施。H△Gの核心にあるものや、“昼系”アーティストとしての今後のビジョンを語ってもらった。
◆ ◆ ◆
■どんなものにも染まれることが、不思議な魅力
──H△Gはビジュアル露出がないだけでなく、ボーカルのChihoさんを軸に置いたプロジェクトチームなので、とても匿名性が高いです。まずどのようなバックグラウンドを持っているのかおさらいしてもよろしいでしょうか?
丹羽文基(所属事務所代表):2012年から始動していて、ネットに楽曲を投稿するだけというスタンスを取っていたんですけど、発端はライブハウスシーンなんですよね。岡崎でライブハウスを運営していた石川さんが、当時盛り上がりを見せていたネットシーンに着目して、地元のバンドマンとタッグを組んで始まったプロジェクトなんです。supercellをベンチマークにしていたんですよね。
──初期の制服のアーティスト写真は、supercellのオマージュだったんですね。
丹羽:石川さんとは古い付き合いなので“こういうプロジェクトをやろうと思っているんだ”という話は立ち上げの段階から聞いていたんです。
峯松亮(所属レコード会社A&R):その頃丹羽さんはドリーミュージックにいて、制作ディレクターをなさっていたんですよね。
丹羽:だから当時「ドリーミュージックからデビューしてみるのはどう?」と声を掛けてみたんですけど、「そういう気はないです」ときっぱり断られていて。でもH△Gもネットで投稿を重ねていくうちに反響が大きくなっていって、チーム全体にも心境の変化があったのか「もっと上を目指したいです。一緒にやりませんか?」と声を掛けてもらって。僕がH△Gとちゃんと関わるようになったのは2016年なんですけど、そのあたりからsupercell色が薄くなりましたね。僕としては宝塚をベンチマークにしたくて。

▲丹羽文基氏
──宝塚歌劇団ですか?
丹羽:メンバーが矢面に立たないグループなので、最も前面に出るのが“H△G”なんです。ブランドそのものに人格を持たせられて、そこにファンがつく──“H△G”がひとり歩きしてくれたらと思ったんです。それで世界観を押していくことにしたんですよね。ニコニコ動画からYouTubeにシフトしていったのも、そのタイミングです。
──H△G側の心境の変化に沿って、ブランディングをシフトチェンジしたということですね。なぜ彼らにそのような心境の変化があったのでしょう?
丹羽:H△Gのメンバーは全員社会人で、自分の生活基盤がしっかりあるんです。だから職業アーティストを目指していない。ただ好きで、活動を続けたいという気持ちだけで音楽をしていた人たちなので、デビューすることで生活も音楽活動もやりにくくなると思っていたのかもしれないですね。でもリスナーや受け手の期待が大きくなって、それに応えたい気持ちも膨らんでいって──これは想像ですけど、やっぱりライブがH△Gチームを変えたのかなと思いますね。生の反応を見ることによって、気持ち的にも動いていったのかな。
──H△Gはその後、2017年5月にはVOCALOID楽曲のカバーアルバム『声~VOCALOID Cover Album~』をリリースします。
丹羽:その反響が大きくて、ネットシーンからさらに広がるために徳間ジャパンさんからメジャーデビューを決めました。活動方針の違いが多かったことから1年で契約を終えて、自分たち主導の活動をしていくなかでドリーミュージックさんというパートナーに出会うんですけど、そのきっかけが“声劇ライヴ”で。
──2019年3月に行われた、音楽と小説と朗読を融合させたワンマンライヴですね。H△Gの楽曲「銀河鉄道の夜を越えて」と人気ライトノベル『月とライカと吸血姫』のコラボレーションとして展開されるという。
峯松:前の担当がそのライヴを観て声を掛けたところから、ドリーミュージックベースで配信シングルをリリースするようになりました。僕はそのあとにドリーミュージックに入社して、H△Gの担当に付かせてもらったんですよね。だから声劇を観たのもメンバーに会ったのも2020年3月にリリースしたBlu-rayアルバム『瞬きもせずに』用の再録のタイミングなんです。事前に思い描いていた以上のクオリティ、クリエイティブへのこだわりにも驚きましたけど、特に衝撃的だったのはChihoの声でした。このアーティストに携われる喜びや野望が湧いていった瞬間でしたね。
──H△Gは日本語でしか表現できない“懐かしい”や“切ない”といった概念を世界中に発信していく次世代J-POPアーティストというキャッチフレーズがついています。
峯松:H△Gのもともとのキーワードは“青さ”だったんですよね。
丹羽:でも“青さ”だけだとちょっとぼんやりしているので、具体的に“青春”や“切ない”、“別れ”といった日本的な世界観というワードを出して組み立てていって。ネットシーンで活動していたとはいえ、やっぱりそれまでは“ロックバンド”だったんですよ。でも序盤で話したとおり宝塚的な見せ方にシフトチェンジしていくなかで、音楽性の幅を広げることにしました。もしかしたら人によってはサウンドが古くなったと感じたかもしれない。でも、それはそれでいいことかなと思ったんです。
──それ以上にいろんなジャンル感を取り入れることを重要視なさったということですよね。だからこそ今、H△Gはテレビドラマ、テレビアニメ、CMなど多種多様なタイアップに柔軟に対応できている。
峯松:タイアップ作品の世界観やクライアントさんの意向に寄り添いながらも、H△Gのアイデンティティやクリエイティブな要素を生み出すことができるのは強みだと思いますね。それは引き出しの多さにもつながっているんじゃないかな。どんなものにも染まれることが、不思議な魅力になっている。
丹羽:ネットカルチャーにのめり込んでいる人たちにあまり馴染みがないところからアイデアを拾ってくることは昔から多くて。それはもっと多くの人たちに聴いてもらいたい気持ちと、ほかのクリエイターとは毛色が違うことを主張したい気持ち、両方から来るものなんですよね。結果H△Gは振れ幅が大きいアーティストになっていって。それはすごいことだと思うんですよ。
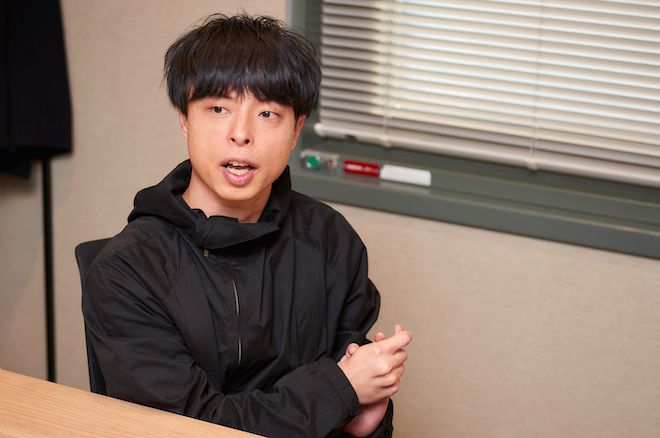
▲峯松亮氏
──H△GのメインコンポーザーのYutaさんは、もともとパンク畑の方ですよね?
峯松:そうです、そうです。Yutaは3コードが大好き(笑)。
丹羽:もっと言えば石川さんもそうですね。だからH△Gの根幹にあるマインドは、反骨精神やパンクスピリットなんですよ。そこに“青春”がコーディングされていて、そこに僕が“こんな服を着てみるのはどう?”と提案する──そんなバランスなんです。匿名性を持たせて音楽性を広げながらも、その背骨だけは崩さないようにしてきましたね。そこだけは間違わないようにしてきました。
峯松:ブランディングとして匿名性を出していたところもあるので、インタビューなどでChihoもYutaもどう話したらいいのか難しいところはあったと思うんです。でもネットシーンはさらに盛り上がっているし、メディアのみなさんのお力を借りながらH△Gのアーティスト像は徐々にベールを脱ぎ始めている……という状況が今ですね。最近Yutaから上がってくるデモから、彼なりにいろんなものを吸収していることが伝わってくるんです。僕は丹羽さんと違って制作というよりは宣伝畑寄りの人間ではあるんですけど、つい数日前に「このアーティストのこのバラードを聴いてみてもらえない?」と提案してみて。今の彼ならそれを噛み砕けるし、+αで自分を上回るものを作れる気がしたんですよね。







