【インタビュー】松室政哉、音楽による短編映画集“封切り”

その歌はまるで映画のように、様々なエピソードを連ね、喜びと悲しみを積み重ね、やがて美しく壮大なエンディングへと進んでゆく──。稀代の映画フリークとして知られるシンガーソングライター・松室政哉が新たに立ち上げたのは、楽曲世界を視覚的にも更に広げていく「Musicalize Project(ムジカライズプロジェクト)」という深く豊かな表現のかたち。新作ミニアルバム『Touch』はその第一弾で、一つのラブストーリーを軸にした、いわば音楽による短編映画集だ。躍動するバンドサウンドと繊細な打ち込み、キャッチーなソウル・ポップと王道バラード、明るく弾む恋模様とせつない別れ、いくつもの大きな振り幅の中で描かれるストーリーは、すべてを聴き終えたあと、あなたの心にどんなシーンを浮かび上がらせるだろう? ようこそ、松室政哉の、映画のような音楽の世界へ。
◆ ◆ ◆
■頭の中で映像化してもらう
──今回は、コンセプトアルバムということで、今までと、作り方からして違う感じですか。
松室:そもそも、ミニアルバムというものが初めてなんですね。今まではEPという形態が多かったんですが、たとえば一つ前の『ハジマリノ鐘』は、「ハジマリノ鐘」という、ドン!とした曲が一つあって、他の曲はバラエティさもいろんな方向に向いたおもちゃ箱的な感じで。でも折角ミニアルバムという形で表現するなら、しっかりした枠があったほうがいいなと思って、「Musicalize Project」というコンセプトを立ち上げたんですね。もともと僕は、映画がめちゃくちゃ好きで、頭の中でいろんな映像を浮かべて、それを音に落とし込む、歌詞に落とし込む、ということをやっているんですけど、そうやってできあがったものを、今度は聴いてもらった人の頭の中で更に映像化してもらう、そういうところまで考えながらやっていこうというのが、今回のコンセプトでしたね。
──そうなると、曲の作り方の道筋というか、考え方が、以前とは少し違うわけですか。
松室:そうですね。ここに入っている曲は、去年のコロナ禍の中で出来上がった曲がほとんどなので、そもそも状況が違ったということがありますし、全曲通したコンセプトを決めてアルバムを作ったのは初めてなので、それを意識して作っていったことが、今までとは違いますね。
──去年は、すごく特殊な1年でしたよね。その話も聞こうと思っていたんですけど、コロナで世界が変わってしまった2020年、気持ちの落ち込みのような時期は、やっぱりありましたか。
松室:いえ、実は、そこまで精神的に落ち込むことは、僕はなかったです。曲を作る作業は、もともと家の中でやっているので、あまり変わらないし、自分の曲以外にも、楽曲提供であったりとか、ドラマの劇伴を初めてやらせてもらったりとか、とても充実してたんですね。だから家にはいましたけど、気持ち的にはずっと動いてたので、そこまで落ち込むことはなかったです。ただ、そもそも世界の状況が違うので、その中にいる自分も明らかに違う。そこで何らかの変化はあったと思います。
──これは想像ですけどね。松室さんのように、純粋音楽家体質というか、言いたいことが見つからないと曲が書けないというよりも、音楽を作ることが純粋に楽しいという、そういうタイプのアーティストは、状況の変化にも強いのかな?とか、思ったりします。
松室:そうかもしれないです。僕は、ある種、オタク気質なんですね。映画に関しても、音の作り方に関しても、オタクなんで、そこに入って行ったら、その世界はいつもと変わらずそこにあるから、あまり状況に左右されないところはあるかもしれないです。
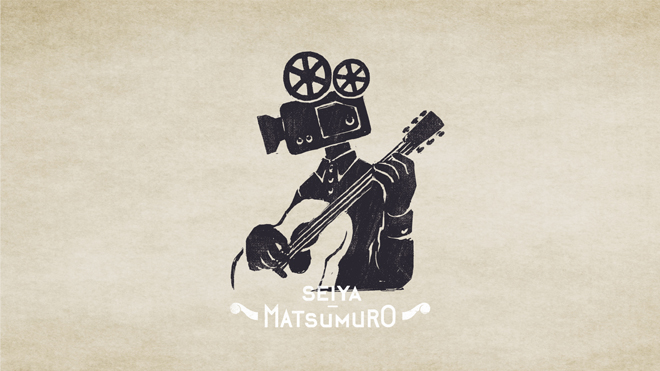
▲プロジェクトビジュアル
──今回の、具体的な曲作りは、どういう作り方ですか。最初に、映像やストーリーを思い浮かべるわけですか。
松室:順番としては、詞はあとです。曲を先に作っていくんですけど、その段階で、打ち込みをしながらアレンジの大枠を作っていって、その時に同時進行で、頭の中に映像が浮かんでますね。それこそ、いろんな映画の断片が浮かぶこともありますし、それがラブストーリーだとしたら、どういう規模のラブストーリーなのか、そういうところも見えてくるし、ただ地球がそこにあるとか、そういう抽象的な映像の時もあるし。サウンドを作っている時の、映像の世界観があって、それを経て歌詞になっていくという感じです。
──たとえば、1曲目の「ai」という曲を例に取ると、どんな映像が浮かんでいたんですか。
松室:「ai」に関しては、アルバムを作っていく中で、一つのテーマになる曲だなと、最初から思っていました。まず、このアルバム全体をラブストーリーにすることは、決めていたんですね。ラブストーリーと言っても、失恋の曲なのか、別れを予感させる曲なのか、いろんな種類があると思うんですけど、「ai」は、まだ出会って間もないような歌で、ただキラキラした喜びというよりは、どこかに不安を感じている主人公がいるんですね。それはまぎれもなく、コロナという状況が大きかったなと僕は思います。タイトルの『Touch』というのもそうですけど、当たり前にしていたことが、コロナによって遮断されたんですね。「Touch=触れる」ということが。だから、普通にラブソングを書こうと思って始まったものが、こういうふうになったというのは、結果論ですけど、コロナの影響をめちゃくちゃ受けてるなって思います。
──「ai」で始まり、「Touch」で終わる曲順には、一つのストーリーの流れがあるんですね。
松室:そうなんです。時系列も考えて、並べてますし。
──確かに、そうですね。出会いの曲から始まって、幸せな時間があって、やがて暗雲がやってくる。3曲目の「PUZZLE」では、すでに別れの影が差し込み始めているし、4曲目「Cube」ではそれが隠しようもなくはっきりしてくる。
松室:その間に何があったのか?を、想像してもらうのが、映像になるんですね。一つ一つのチャプターがあって、そこに至るまでに何があったのか?は、聴いた人それぞれが違うと思うし、それを想像するということは、頭の中に映像が浮かんでいるので、それが「聴いてもらった人の頭の中で映像化してもらう」ということになるのかなと思います。
──「ai」が出会い、次の「hanbunko」が、未来を見つめる幸福な時間。そして「PUZZLE」で不穏な空気が漂い始めて、おやおや?と。
松室:何があったの?と。起承転結じゃないですけど、明らかにそういう流れがありますね。映画の話になりますけど、映画の中で印象的な曲が流れるシーンって、たとえば一つの事件が起きた、その瞬間にはあんまり印象的な曲は流れない。事件が起きて、そこに振り回されていく、それに伴う感情の変化の時に、印象的な音楽が流れることが、僕は多いと思うんですよ。だから今回の曲も、そういう印象かもしれない。1曲1曲で「何が起こったのか?」というふうに、ストーリーを描く曲の作り方も出来たと思うんですけど、それは逆に、あまり映像的にはならないかな?と。
──説明しすぎないで、行間を読むということですね。そう考えると、「PUZZLE」は重要な曲ですね。まさに、何らかの事件が起きたあとの心の動きを、すごく繊細に描いていて、想像力をかきたてられる。「PUZZLE」を作った時は、どんなイメージが浮かんでいたんですか。
松室:これも曲が先に出来ていたんですけど、二人の恋というものがだんだん、こうなって(下がって)行く、そういう曲になるだろうということは、まだ歌詞が出来てない時から思っていたんですね。マイナーコードが多い曲ですけど、リズムはけっこうハネていて、そういうのも映像的なのかな?と思います。たとえば、サスペンスものの映画を見ていて、殺人シーンがあった時に、すごく優雅なクラシック音楽が流れてきたら…。
──逆に、怖いですね。
松室:そうなんです。そういう相反するものが、怖さとか、切なさになっていく。この曲に限らず、そういう発想や作り方をすることは多いかもしれないです。あったかい、キラキラしたサウンドなのに、歌詞はすごくせつないとか。「PUZZLE」もそういう発想ですね。
──「PUZZLE」は、軽くスウィングするピアノポップで、おしゃれなスキャットを入れたりして、聴き心地が爽やかなんですけど、今言われたように、詞に陰りがあるんですね。そこが魅力だと思います。対照的に、その次の「Cube」は全編打ち込みの、パーソナルな質感と、クールさと、不思議な浮遊感が面白い曲。
松室:ここは、全体のストーリーの流れの中で、もう一個「落とす」ところなんですよ。サウンド的なことも考えていく中で、「PUZZLE」がしっかりとしたバンドサウンドなので、それとは違う手で落としていくことが必要だなと思って、結果、こういう打ち込みの曲になって、コーラスも多めになりました。
──確かに、ここでバンドサウンドで、せつなさたっぷりに歌われたら、ちょっとトゥーマッチかもしれない。
松室:そうなんです。あえて突き放すような感じもあります。







