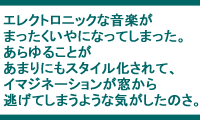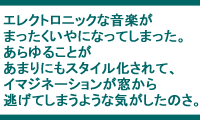 | Juno Reactorのリーダーで、この10年間にオリジナルのテクノアルバム5枚と、ヒット映画『Mortal Combat』のサウンドトラックに提供した2曲で富を築いた男、Ben Watkinsが驚くべき告白をした。「'98年の『Bible Of Dreams』ツアーが終わってから、エレクトロニックな音楽がまったくいやになってしまったんだ」と彼は認める。
「あらゆることがあまりにもスタイル化されて、イマジネーションが窓から逃げてしまうような気がしたのさ。みんながドタバタしたサウンドを作って、バスドラの音を上げれば充分だと考えるようになってしまった。ファンタジーとか音楽について僕が気に入っている要素がすべてなくなってしまったみたいだ。そうしたヘヴィなサウンドのビートを聞くたびに、本当に気分が悪くなったんだよ。だから、そこから逃げ出したのさ」つまり、Ben Watkinsはグルーヴを取り戻す必要があったのだ。
そして2年以上がたち、Juno Reactorは最新作『Shango』を引っ提げて戻ってきた。そこでのWatkinsは自分のグルーヴを取り戻しており、グループの過去の財産でトレードマークであるハイエナジー・テクノと同様に、ワールドミュージックからの影響の増大を聞き取ることができる。個々のトラックにはSteve Stevens(Billy Idolのバンドのギタリスト)による機敏なスパニッシュギター演奏、力強いドラミング、南アフリカのアンサンブルAmampondoのメンバーによるチャント、そしてTaz Alexanderによる言葉のない魅惑的な女性ヴォーカルといった様々な生音の要素が含まれている。Juno Reactorはアフリカ、中東、さらにマカロニウェスタンの美学を1つのアルバムで統合したという点だけで、支持に値するグループである。
'96年の『Beyond The Infinite』における高速ゴアトランスや、'98年の『Bible Of Dreams』でのうっとりさせるトライバルテクノからの印象的な進化は、彼らの音楽の映画的な性質を考えれば極めて意味のあるものだ。「僕はまるで欲求不満の映画監督みたいな気分だったよ。あらゆる曲が何らかの意味を持っていなくちゃいけないって感じでさ」とWatkinsは説明する。「聴衆を跳びはねさせるためだけの音楽を作るつもりはないよ」
正直なところJuno Reactorの音楽は確かにリスナーを跳びはねたい気持ちにさせるが、それだけでなく一緒に歌いたい気分にもさせてくれる。だが、特に今回のケースでは“欲求不満の映画監督”という表現は的を射ている。というのも『Shango』は'99年に公開されたChristopher Lambertの映画『Beowulf』のサウンドトラックを、Watkinsが担当したことに端を発しているからだ。「どっちかっていえば、ガラクタ同然のしょうもない映画だったけどね」Watkinsは笑いながら言い放った。「だけど僕にとってフィルムのスコアは初めての経験だったから大きなチャンスだったし、楽しみながらトライできたので良かったと思っている」
最近のエレクトロニック戦線から離脱するという経験によって、Watkinsのクリエイティヴ面のバッテリーは再充電され、『Shango』のために最初に書かれラストに収められた「Song For Ancestors」を書くに至ったのである。アコースティックなジャムセッションから派生した曲で、Watkinsがアコースティックギターを弾き、Alexanderが歌を、Busi Mhlongoがチャントを、Mabi Thobejaneがアフリカンドラムとチャントを各々担当している。「Song For Ancestors」は南アフリカの“魂を呼び出す”儀式にインスパイアされたという。後にシンセ的なタッチが加えられているものの、最終的には多くのリスナーを驚かせるであろうメロウなワールドミュージックに仕上がっている。だが、多種多様なムードとテンポに乗せて、オーガニックとエレクトロニックな要素が常に織り混ざっているアルバム全体からは、決して浮き上がっているわけではない。
まるで優れたワイン商人のように、Watkinsは時が来るまで新しい音楽をリリースすることはせず、熟成する時間を与える方法をとった。このアプローチは、驚くほど急速なペースで生産される最近のエレクトロニック音楽の性質に逆行するものである。この点に関してWatkinsは批判的だ。「みんなが僕に言うんだ、“このトラックにそんなに時間をかけるなんて愚かだよ。試してみて数日で仕上げたら”ってね。でも思い付いた曲を3日で完成させてしまえば、以前のアルバムと同じようなものになってしまいそうでさ」というのが彼の見解である。「一息ついてから曲自身の命を見つけてやるための時間が必要なんだ。何か違ったものを見つけようとするときには…、僕自身の音楽でのキャリアから言えるのは、技術的な面でも創造的な面でも大きな経験曲線が存在するということだよ」
Watkinsと仲間たちは『Shango』の9曲のうち7曲を1カ月かけて完成させた。「Nitrogen Part 2」は5日間で仕上がったが、それはアルバムがまとまりかけている頃のことである。もう1曲の例外である「Solaris」はわずか4回のセッションで完成したが、各回は5年間にまたがっており、インディアンフルート奏者のDeepak Ram、Tuvanの喉声シンガーであるBoris Salchach、ペダルスティールギタリストのB.J. Cole、タブラの名人Pan dit Dineshといったゲストが参加している。
ニューアルバムをついに完成させた今、Juno Reactorの次なるチャレンジは彼らのエキゾチックなサウンドをライヴのオーディエンスに届けることだろう。Mobyをサポートした前回の米国ツアーで、Watkins(自身はキーボードとギターを演奏した)はAmampondoのメンバー12名を招いて、音楽に必要なエスニックな要素を持ち込んだ。このうち5名はこの10月にスタートした秋の北米ツアーにも再び参加しており、またアルバムのトラック「Nitrogen Part 2」にも貢献したOrbのシンセ奏者Alex Patersonも同行している。ヴィジュアル面ではAmampondoが彼らの部族the Xhosa(発音はAh-kosa)を象徴する伝統的な衣装と羽つき帽を身に付けているという。
Amampondoは存在そのものの性質からして、Junoの音楽に強度を注入している。同グループは20年にわたって活動しており、アパルトヘイトの中を生き残ってきた。「南アフリカの警察は一度は彼らを殺そうとしたんだ」とWatkinsは明言する。「Mike Ludongaに銃弾を5発、他のメンバーにも数発ずつ打ち込んで、見殺しにしたのさ。その後の混乱が静まるまで、彼らはイスラエルで1年間も身を潜めていた。彼らには驚くべき話がいっぱいあるよ。彼らはランガに住んでいるんだけど、そこは街区暴動と黒人の良心の中心地でもあるんだ。僕が仕事をした中で最も素晴らしい人々であるのはもちろん、彼らは僕が出会った中で最も優れたミュージシャンでもあるのさ。彼らは僕を驚かせるのと同時にインスパイアしてくれるんだ。本当だよ。彼らには他の人達とは違うパワーがあるんだ」
Juno Reactorの折衷主義は一部の人にとっては異端的に思えるかもしれないが、これは各々が受けた影響を集積した究極の産物なのである。Amampondoは別にしても、ベーシストのStefan Holweck、ドラマーのNick Burton、エンジニアのGreg Hunterといった何度もJunoに参加したプレイヤーは、それぞれ過去にKilling Joke、Jah Wobble、Orbといったアーティストと活動しており、ドラマーのMabi Thobejaneは'70年代にMiles Davisとライヴ演奏をした経験を持つ。Watkins自身も'80年代初頭からEmpty Quarter、the Flowerpot Men、Sunsonic、Psychoslapheadといったpre-Juno的なグループでエレクトロニック音楽を作ってきた。彼はまたTraci Lordsの'95年のテクノデビュー作『1,000 Fires』の4曲を共作および共同プロデュースしたほか、Allison Moyet、Devo、Siouxsie & the Bansheesといったアーティストのプロデュースあるいはリミックスを手掛けている。
だが結局のところJuno Reactorの最も重要な側面は、彼らが過去に何をやってきたのかではなく、彼らが現在のエレクトロニック・ダンス・ミュージックの視野をいかに拡張しているかということなのだ。Watkinsは今日のDJカルチャーに言及して、“メッセージは好きだが、メッセンジャーは嫌い”という古典的なジレンマを表明した。「ほんとはこんなこと言うべきじゃないと思うこともあるよ。だって僕たちの曲をプレイしてくれる世界中のDJからずいぶんサポートしてもらったからね」とWatkins。「でもシーンは完全な無秩序状態だと思う。今に何かが現われてすべてをかっさらっていくだろう。僕はそれを待っているのさ」 |